|
|
|
|
|
|
|
|
|
�ǂ��Ȃ��Ă���w�r��Q�J��
|
|
|
|
�F���x�̕ϑJ |
|
|
|
�� ���@�t �v *
|
|
|
|
|
�@�u�r��Q�̘J�ДF�肪���������B�v����ȉ�b�����ɂ��邱�Ƃ������Ȃ�܂����B�u�E��ɂ������r�nj�Q�\�h��Ɋւ��錟�����ʕ��i�����V�N�W���j�v�i�����J���ЊQ�h�~����j�́A�E��ɂ������r��Q�ǂ����Ȃ����߂̍�ƊǗ��A��Ɗ��Ǘ��y�ь��N�Ǘ��ɂ��Ă��悻�T�N�����Ē����E�����̂����܂Ƃ߂�ꂽ���̂ł��B
�@�Ƃ��낪�A���̎w�j����傫����E����ȘJ�������̂��ƂŔ��ǂ��A�����Ԃ̗×{��]�V�Ȃ�����Ă���늳�҂��J�ЂƔF�肳��Ȃ��P�[�X���U������܂��B����ł��r��Q�̘J�ДF��͂Ȃ��̂��Ǝv���ƁA���܂茵�����J�����ԂƎv���Ȃ��y���̐l�ɂ͘J�ЂƔF�肳���l���o�Ă���̂ł��B����Ȏ����璷���Ԃ̗×{��]�V�Ȃ������u�d�ǎҁv�͘J�ЂƔF�肳�ꂸ�A��r�I�Z���Ԃʼn���u�y�ǎҁv�͘J�ЂƔF�肳���H����Ȃ��ƂɂȂ��Ă���̂��Ƃ����^�₪�N���Ă���̂ł��B
�@����A���{�Y�Ɖq���w���r��Q�������u�r��Q�̒�`�E�f�f��E�a�����Ɋւ����Ăɂ��āv��N���ꂽ�̂��@�ɁA�r��Q�̘J�ДF��̗��j��U��Ԃ�A�����̘J�ДF��Ɩ��̈�E�ƕa���̗������������s���Ă��Ȃ��w�i��T�邱�ƂƂ��܂����B
|
|
|
| �ǂ��Ȃ��Ă���J�ДF��Ɩ� |
 |
|
�@�J���҂��d���������ŃP�K��������a�C�ɂȂ��Ĉ�҂Ɋ|����A���̔�p�͎g�p�҂��S�z���S���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B�J����@�ɂ́A�������L����Ă��܂��B�i�J����@��75���j�ᔽ����U�ӌ��ȉ��̒��͌ܐ�~�ȉ��̔����ɏ������܂��B�i�J����@��119���j�����ɁA�J����@��W�S���͘J���ҍЊQ�⏞�ی��@�ɂ���ĕی����t���s��ꂽ�ꍇ�ɂ́A�g�p�҂͕⏞�̐ӂ�Ƃ��Ƃ���Ă��܂��B�]���Ėw�ǂ̊�Ƃ��J���ҍЊQ�⏞�ی��@�ւ̉������`���Â����Ă��鍡���A�Ɩ��ЊQ�̕⏞�ɂ��Ă͘J�Еی��̎x���ΏۂƂ��ꂩ�ۂ��������ꓹ�ɂȂ�܂��B
�@�Ƃ���Ŏ��������P�K��������a�C�ɂȂ��Ĉ�҂Ɋ|���鎞�A���̔�p�����N�ی��ƘJ�Еی��̂ǂ���ŕ��S����̂��Љ�펯�ɍ��v���邩�A�l���Ă���l�ǂꂭ�炢����ł��傤�B����Ȃ��Ƃ��܂�ӎ����Ȃ��ŁA�m�炸�m�炸�̓��Ɍ��N�ی��̕���I��ł���l�������Ȃ��ł��傤���B
�@�̂���g�P�K�ƕٓ��͎�O�����h�ƕ�������Ă������Ƃ��L��ł��傤���A��Ђ��猙���点������ċ߂��Ȃ��Ȃ�A����ȐS�z���L��ł��傤�B�Ƃ�킯���a�̏ꍇ�ɂ́A�����̂悤�ȃP�[�X���ʂ����ĘJ�ЂɔF�߂��邩�ۂ��A�ؖ�����̂������̋�J�ł͂Ȃ��E�E�E���A�J�ДF��ɑ���s�����傫���Ђ��Đ\�����S�O�����Ă���Ǝv���܂��B
�@������グ���r��Q�̘J�ДF����A�������ǂ�Ώ��a30�N����{�����x�o�ϐ�������̂��Ǝ����������̗v�Ƃ��ēd�Z�@���������Ƃɒ[���Ă��܂��B�d�Z�@���E�@�B���ɓK�������邽�߂ɍ�Ɠ��e�E�J����������I�ɕύX����A�V���Ȍ��N��Q�Ƃ����r��Q�i�����́u���傤���v�j���o�����܂����B�������A���{��o�c�҂����͌��N�j��̌��������Ɣ�Ў҂̋~�ρE���R�h�~����ɂ������߁A���N��Q�͋}���ɐ[�������܂����B
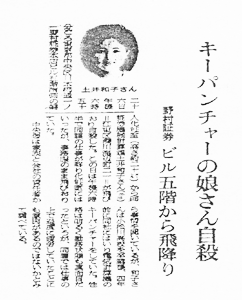 �@�w�W���ߑO�W���T���A�������c���蒬�P-�U�A���c�ЊC��r���U�K�̏��q�X�ߎ������瓯�ЃL�[�p���`���[�A�ђˋv�q����i�P�X�j����Q�O���[�g�����̃R���N���[�g�ʘH�ɗ�����11���������B�ђ˂���͍�N�S�����Z���ƌ���ЁA�Q�����̌��C���Ԃ̂��ƌ���ɔz������L�[�p���`���[�����Ă����B �@�w�W���ߑO�W���T���A�������c���蒬�P-�U�A���c�ЊC��r���U�K�̏��q�X�ߎ������瓯�ЃL�[�p���`���[�A�ђˋv�q����i�P�X�j����Q�O���[�g�����̃R���N���[�g�ʘH�ɗ�����11���������B�ђ˂���͍�N�S�����Z���ƌ���ЁA�Q�����̌��C���Ԃ̂��ƌ���ɔz������L�[�p���`���[�����Ă����B
�@�L�[�p���`���[�͒P���ȍ�Ƃ̘A���ł��邽�߃m�C���[�[�ɂ�������̂������A���N�Q��26���A��������{���̖쑺暌��{�Ђł��L�[�p���`���[���T�K�����э~�莩�E���Ă���B�x�i����͏��a37�N10���W���t�������V���̋L���ł��B�j
�@���̂����܂����j���[�X�́A�����A���y���͂��߂������@�B���ɔ����ēo�ꂵ���L�[�p���`���[�Ƃ����V���������̐E�ƂɁA���炽�߂ĎЉ�̒��ڂ��W�߂����܂����B
�@���u�ł��Ȃ��Ȃ����J���ȁi�������J���ȁj�́A���a38�N�Ɂu�L�[�p���`���[�a��̐��Ɖ�c�v��ݒu���A�����a39�N�Ɂu�L�[�p���`���[�a�̊Ǘ���v�Ɓu�Ɩ���O�̔F���v��ʒB���܂����B
�@�r��Q�̘J�ДF���͂���܂ōŏ��̐�����܂߂S�x��������Ă��܂��B���̘J�ДF���Ƃ������̂́A���̐��i��쐬�ɂ������Ă͔�Ў҂̑����~�ςƑ�������ɗ�����Ɠ����ɁA�\�h�E�Ĕ��h�~�ɂƂ��Ă��傫�Ȏw�j�ƂȂ���̂łȂ���Ȃ�܂���B
�@�]���āA�F���̓��e�Ƃ��ẮA���ɔF�肳��Ă��鑽���̎������ɁA�܂��r��Q�͂ǂ̂悤�ȕa�C�Ȃ̂��A�ŐV�̈�w�I�i���Ɍ����������̓����I�ȕa���A�o�߁A�����Ȃǂ����������f���ꂽ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@���̎��_����A�r��Q�J�ДF���̂S�x�̉������ǂ̂悤�Ȏ���w�i�̌��ŁA�ǂ̂悤�Ɏ��{����Ă����̂��������邱�Ƃɂ��܂����B
|
|
|
| �J�Е⏞���x�̊T�� |
 |
|
�@�J���҂��d���������ŕ���������a�C�ɜ�����Ƃ��A�܂��A���S�����莡�����������Q���c�����肵���ꍇ�ɁA�g�p�҂͂��̎��Ô���x�����i�×{�⏞�j�x�ƒ��̒�����⏞���i�x�ƕ⏞�j�A���邢�͌���Q�ɑ��Ă̏�Q�⏞��A�⑰�⏞�Ȃǂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����u�ЊQ�⏞�v�̋`���́A�J����@�̑�W�͂Œ�߂��Ă��܂��B�����āA���̐ӔC�S�ەی��Ƃ��āu�J���ҍЊQ�⏞�ی��@�v�ɂ��J�Еی�������܂��B
�@���ƌ������̏ꍇ�ɂ͍��ƌ������@�y�э��ƌ������ЊQ�⏞�ی��@�A�n���������̏ꍇ�ɂ͒n���������@�y�ђn���������ЊQ�⏞�ی��@�A�܂��D���̏ꍇ�ɂ͑D���@�y�ёD���ی��@�ɂ���ĕ⏞���邱�ƂƂȂ�܂��B
�@�u�Ɩ���v�������A�܂��͎��a�ɂ���������Ў҂ɑ��ẮA�K�v�Ƃ���×{�̋@����\���ۏ��ĐE�ꕜ�A�������͎Љ�A���͂���ƂƂ��ɁA��Ўҕ��тɂ��̈⑰���u�l����ɒl���鐶�����c�ނ��߂̕K�v�����ׂ��v�ی�����邽�߂̘J���@��̖@��~�ϐ��x�ł��B�i�J����@��P��J�������̌������тɘJ���ҍЊQ�⏞�ی��@��P��ړI�j
�@���̂悤�ɖ@���ŕۏ��ꂽ�u�ЊQ�⏞�v�́A��ЎҖ{�l�܂��͈⑰���⏞���t�������邱�Ƃɂ���Ďx���������̂ŁA�X�̎��a�A�����A���邢�͎��S�ɑ��ĕ⏞�̎x���A�s�x���̌���͘J����ē����i�������ɂ��Ă͊e���{�@�ւ�l���@�Ȃǁj���s���܂��B���̍ۂɋƖ���ł��邩�Ȃ����肷��̂��A������u�J�ДF��v�ł��B
�@���̂悤�ȘJ�Е⏞���x�̕ی���鎖�̏o����⏞�̑Ώۂ́A�@����A�u�Ɩ���v�����A�p���A���S�������͎��a�ƒ�߂��Ă��܂��B
�@�����āA�J����@75���Q���́A�u�Ɩ���v���a�͈̔͂𖽗߂Œ�߂�Ƃ��Ă���A���̋K��ɂ��ƂÂ��A�J����@�{�s�K��35�����u�Ɩ���v���a�͈̔͂��߂Ă��܂��B�i�ʕ\�@�Q�Ɓj
�@��̓I�ɂ͂P�`�V���ŋ�̓I���a����A�X���́u���̑��Ɩ��ɋN�����邱�Ƃ̖��炩�Ȏ��a�v��⏞�ΏۂƂ���ƒ�߂Ă��܂��B�W���́A�V���ȋƖ����a�������ɂ��K�肷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂����A����܂łP��������܂���B�R���ɘJ���p��܂��͘J���ԗl�ɂ��ߏd���S���琶����L�Q���q�ɂ��ߘJ�����a�͋K�肳��Ă���A���a�T�S�N�����ȑO�ɂ́A��I�~�ϋK��ɂ���Ă����~�ς̓����Ȃ������r�nj�Q�A�ߘJ�����ɁA�U����Q���K�肳��Ă��܂��B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �J�ДF��̎��ہi���̋Ɩ���O���f�̂��Ɓj |
 |
�@�J���҂���Ђ������a���J�Е⏞���x�̕⏞�̑ΏۂƂ���u�Ɩ���v���a�ɊY�����邩�ۂ��A�����@�߂́u�Ɩ���v���a�͈̔͂ɗ��ꂽ�ǂ́u�Ɩ���v���a�ɊY�����邩�ۂ��̔��f�����邱�Ƃ��u�Ɩ���O�F��v�Ƃ����܂��B
�@�J���ȁi�������J���ȁj���Ɩ��Ǝ��a�̈��ʊW�ɂ��āA���̊�{�I�l�������܂Ƃ߂����̂��u�J�Е⏞�@�Ɩ���O�F���̏ډ��v�i���a43�N�V��15���j�ł��B
�y�@��Ɂu�J�Е⏞�Ɩ���O�F��̗��_�Ǝ��ہv�u�Ɩ��ЊQ�y�ђʋЊQ�F��̗��_�Ǝ��ہv�Ɍp���@�z
�@�����J�АE�ƕa���Ɋւ��悤�ɂȂ����̂͏��a44�N�ł��B�����ōŏ��ɔF�蓬�����������邽�߂ɏn�ǂ��Ȃ����ƑE�߂�ꂽ�̂��A�u�J�Е⏞�@�Ɩ���O�F���̏ډ��v�ł����B�ŏ��A�Ȃ́u�r�nj�Q�E���ɏǁv�̘J�ДF�蓬������X�^�[�g���A���̌�A���ŁE����x�E�A�X�x�X�g�E�ߘJ���E���E�E��ʍЊQ�c�Ɛ������̘J�АE�ƕa�F�蓬���i�܂�������P���j�Ɍg����Ў҂Ƌ��ɓ����Ă��܂������A�ǂ�Ȏ��Ăł����_�͂��́u�J�Е⏞�@�Ɩ���O�F���̏ډ��v�Ŏ�����Ă��鍑�̔��f��ł����B
�@���ɏЉ��ꕶ�́A�J���ȁi�������J���ȁj�J����ǂ̏��r�_�v���ǒ��i�����j���܂Ƃ߂��A�e��W��ł����ނƂ��Ďg�p���Ă������̂ł����A���̊�{�I�l�����͍������ς���Ă��܂���B�ǂ�ł���������Ε�����Ǝv���܂����A�����ɂ͓�����O�̂��Ƃ���������Ă��܂���B�Ƃ��낪���́u��{�v�����E���A��Ў҂̊�{�I������D�������͏�ɂ������Ă���A���������͂��̐��ʂɖ��f�����肷��Ɖi�N�̋�J�̖��l���������ʂ܂ō��������D���Ԃ���Ă��܂��ꂢ�̌������Ă��܂����B�r��Q�J�ДF���̐�������������l�����ł��d�v�ȍl������������Ă��܂��̂ł����Ɉ���������̂܂܌f�ڂ��܂����B |
|
|
| �@��b���a�A�f���A�������a�ƋƖ���O���f�̊W |
 |
| �@(1) �p��̉�� |
 |
�@�Ɩ��㎾�a���l����ꍇ�ɁA�ǂ����Ă����O�ł��Ȃ��̂��A��b���a�A�f���A�������a�Ƃ������̂Ƃ̊֘A�ł���܂��B�����͐g�̓I�ɂ��ُ킪�Ȃ��S�����N�Ƃ����҂��ܘ_����܂�����ǂ��A���炩�̑f���Ƃ������̂������Ă���A���邢�͊�b���a�Ƃ������̂�����A���邢�͊����̎��a�Ƃ������̂������Ă��邢�����Ƃ��������킯�ł��B���������ꍇ�ɁA�Ɩ��Ƃ̊֘A���������Ƃ��Ă��A���Ƃ��Ɩ{�l�̊����̎��a������������A����͋Ɩ���ɂȂ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA���ɖ��ł��B�]���܂��āA���Ƃ��f���A���邢�͊�b���a�Ƃ��������a�Ƃ��������̂�����܂��Ă��A��͂肻��ɋƖ��Ƃ������̂�������x��p�����Y���a�ǂ������Ƃ��A�����������Ƃ������Ƃ��͂����肢�����܂���A����͋Ɩ���Ƃ��Ď�舵���Ă������ƂɂȂ��Ă���̂ł���܂��B
�@�f���Ƃ����̂͂ǂ������ꍇ���Ɛ\���܂��ƁA���Ƃ��Ƃ��̐l�ɂƂ��Ă��鎾�a�ɂ�����Ղ��悤�ȑ̎�������Ƃ������Ƃł���܂��B�Ⴆ�ΈȑO�悭�����܂����y�j�V�����̃V���b�N�����Ƃ��A�����M�[�̎����Ƃ������悤�ȏꍇ�ɂ́A�����������a�ɂ�����Ղ��悤�ȑ̎��Ƃ������̂��{�l�ɂ���킯�ł��B�����ŁA�Ⴆ�f��������܂��Ă��A��͂�Ɩ��Ƃ������̂���p���ďǏ����������Ƃ����炩�ł���ꍇ�ɂ́A�Ɩ���̎��a�Ƃ��Ď�舵���Ă������ƂɂȂ��Ă���܂��B
�@��b���a�Ɛ\���܂��̂́A�]�o���̏ꍇ�̍�����������܂��B�]�o�����N���������ɁA���Ƃ��Ɩ{�l���������ǂ���b���a�Ƃ����悤�ɌĂ�ł���̂ł���܂��B���������ꍇ���{�l���������ǂł���������Ƃ������ƂŁA�Ɩ��O�̎戵������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA��͂�A�Ɩ����ǂ������`�łǂ������ӂ��ɍ�p���Ĕ]�o����������Ă��Ă��邩�Ƃ����悤�Ȏ����A�悭�����������ċƖ��ォ�O���f���邱�Ƃɂ��Ă���̂ł���܂��B
�@�������a�͔��ɖ��ɂȂ�ꍇ������܂��B�������a�Ɛ\���܂��ƁA�Ⴆ���ɏǂ̏ꍇ�̒ŊԔǂƂ����ӂ��ɁA�����ɂ��Ƃ������ƂŐf�f���������Ƃ���ŊԔǂ��������Ƃ����悤�ȏꍇ�ł���܂��B���������ꍇ�ɂ͋Ɩ��ɋN�����ĒŊԔǂ����ǂ����Ƃ��A���Ƃ��Ƃ������ŊԔǂ��Ɩ��ɋN�����đ������A���ɏǂǂ��������Ƃ������Ƃ̗��؍���Ȏ��Ⴊ���Ȃ��Ȃ�����ɂ���܂��B |
 |
| �@�i�Q�j �Ɩ��Ǝ��a�̈��ʊW |
 |
�@������ɂ��܂��Ă��A���Ƃ��f���A��b���a�A�������a������܂��Ă��Ɩ��ɋN�������ЊQ�T�O�ɓ�����悤�ȏo�����������āA����ɂ���Ď��a�����ǂ܂��͑��������ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A�Ɩ���̎��a�Ƃ��ĕ⏞�̑ΏۂɂȂ���̂ł���܂��B�����}�����܂��Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�@�}�@�̏ꍇ�͒N�����Ă�����Ȃ��킯�ł���܂��āA�Ɩ��Ƃ������̂Ɗ֘A���āA���Ƃ��ЊQ���N������Ƃ��ƌ��N�Ȑl�����A���邢�͓]�|�Ƃ��������̂ō����ɕ����Ƃ��Ŗo�������A���ꂪ�����ō��ɂ��N�����Ƃ������悤�Ȃ��ƂɂȂ�B����͂��Ƃ��ƌ��N�ł������l�ł�����A�Ɩ��ɋN�����č��ɂƂ������a���N�������Ƃ������Ƃf����ꍇ�ɂ͈�ԈՂ��킯�ł��B
�@�}�A�͂���l���A�f���Ƃ���b���a�Ƃ������������̂������Ă���B�Ⴆ�������ǂł������Ƃ������ӂ��ɑf���Ƃ���b���a�Ƃ������̂������Ă���Ƃ����悤�ɉ��肵�����̂ł����A���̐l�͏����I�ɂ݂�ƌ��N��Ԃ��珙�X�ɔ��a��ԂƂ����Ƃ���ɍs���\���������Ă���Ƃ����ӂ��Ɍ�����Ǝv���܂��B����������Ԃ̎��ɁA����Ɩ����A����\���グ�܂����悤�ɍЊQ�Ƃ��������̂̂��߂ɁA�����ŋ}���Ɏ��a�����������A���邢�͔��a���Ă��܂����A���Ɏ����𑁂߂Ĕ��a�����B���������ӂ��ɍl������悤�ȏꍇ�ɂ́A��͂�Ɩ���Ƃ������ƂŎ�舵���Ă����Ƃ������j���т���Ă���킯�ł��B������x���肩�����܂��ƁA�{�l�̐g�̏�Ƃ������̂ɁA���Ƃ��Αf��������Ƃ��A��b���a�������āA������͔��a�Ƃ������Ԃ��l������B�������A�Ɩ��Ƃ������̂������ɉ�݂��āA���邢�͏o�����Ƃ������̂������ɉ�݂��āA�������a�̎����Ƃ������̂𑁂߂��Ƃ����悤�ȏꍇ�́A������Ɩ��������������Ƃ����悤�Ȃ��ƂŁA�Ɩ���̎��a�Ƃ����`�ł����F�߂Ă����Ƃ������j���o���Ă���܂��B
�@���̏ꍇ�ɂ悭���ɂȂ�܂��̂��A���Ƃ��ΐS����ჂƂ��A���邢�͔]�����Ȃǂ̏ꍇ�̋Ɩ���O�F��ł��B���Ƃ��A�������ǂƂ�����b���a�Ƃ������̂��������Ƃ��Ă��A��͂肻���ɋƖ�����p���āA���ꂪ���������a�𑁂߂��Ƃ����ӂ��Ɍ�����ꍇ�ɂ́A�Ɩ���Ƃ����`�Ŏ�舵���Ă����悤�ɂȂ�킯�ł������܂����A���̏ꍇ�̒��S�́A�Ɩ��A�o�����Ƃ������̂��ǂ������`�ō�p�������Ƃ������Ƃł��B�]�����́A�F���܂����m�̂悤�ɁA���Ƃ������ŕ֏��̒��œ|���Ƃ��A���邢�͕��ʊ��̏�ł��������܂����悤�Ȍ`�Ŏ��S���Ă���悤�Ȏ��Ⴊ�������鐫�i�̎��a�ł������܂��̂ŁA�}�Q�Ŏ����悤�Ȍ`�Ɍ�����悤�ȋƖ��Ƃ��A���邢�͂ł����ƂƂ��A�����������̂����������ǂ����Ƃ����̂��A�Ɩ���A���邢�͋Ɩ��O�Ƃ������̂ɂȂ錈�߂ĂƂ������ƂɂȂ�킯�ł��B
�@�ł�����A�]�o���A�S���a�Ȃǂł͎��ǂ��Ƃ��ẮA���������o�����Ƃ������̂������Ȃ����낤���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��낢�뒲�������܂��B���ɐ��_�I�ȋْ���ԂƂ������̂��������Ƃ��A���邢�͓��̓I�ɔ��ɉߌ��ȘJ��������Ă�Ƃ��A���邢�͋}�ɂ��̓��ɕs����Ȏd���Ƃ��A�ʏ�̎d���ƕʂȔ��ɕs����Ȏd�������Ă����āA���_�I�ɂ����ɋْ���Ԃɂ������Ƃ������悤�ȁA��͂�d���Ƃ������̂��{�l�ɐ��_�I�Ȃ邢�͓��̓I�ȋْ��Ƃ��������̂�^���A����ɂ���Ă��Ƃ��Ɩ{�l�͂���������b���a������������ǂ��A����ɂ���ċ}�ɔ��a�Ƃ��������̂����߂�ꂽ�Ƃ��A�邢�͑��������Ƃ������悤�Ȃ��̂��F�߂���Ƃ������Ƃł���Ɩ���̎戵��������Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B
�@�}�B�͑O�L�Q�̏ꍇ�ƍl�����͂��Ȃ��ŁA�����Ƃɂ��܂�x�Ⴊ�Ȃ����x�̌y���������a�������Ă��A�Ɩ����������ċ}���ɑ����������Ƃ��F�߂���Ȃ�Ɩ���Ƃ��Ď戵���Ă��܂��B���A�Ɩ��ɋN�����鑝���ł��邩�ǂ�������w��̌o�����ɏƂ炵�ĉ𖾂��Ă邩�A���ɗL�͂Ȍ������Ȃ����ǂ������\���������Ĕ��f���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�}�C�͂�����A�@����Ƃ������̂ł����āA�{�l�̐g�̏�Ԃ����łɎ��a��Ԃɂ���Ƃ��ɁA�Ɩ������܂��܍�p�����Ƃ��Ă��A�u�Ō�̈ꌂ�v�ɂ������A�Ɩ��Ǝ��a�Ƃ̊Ԃɑ������ʊW���F�߂��Ȃ��Ƃ��āA�Ɩ��O�ɂȂ�܂��B |
 |
|
|
 |
|
�@�����Ɏ�����Ă��鍑�̋Ɩ��Ǝ��a�̈��ʊW�ɂ��Ẳ���́A�B�P�ɘJ���s�������łȂ��ٔ��ɂ����Ă���{�ɂ���Ă���l�����ƂȂ��Ă��܂��B���������F�蓬�������������邽�߂ɏ\��������[�߁A�s���E�o�c�ҁE��ÊW�҂Ƃ���������ΘJ�ДF������̂��߂̗v����݂̂Ȃ炸�A��Ў҂��x�����Ă��闧��̐l�������\���������A��Ў҂����a�����r��Q���Ȃ��Ɩ��㎾�a�Ǝ咣���Ă���̂������o����悤���p���Ă����˂Ȃ�܂���B
�@�Ƃ�킯�r��Q�̘J�ДF����тɕ⏞���Ԃ������āA�s�����̕s���Ȍ����̊�ɂȂ��Ă���u���T�X���v�ʒB�́A�Q�ƂR�̑f���E��b���a�̕�����S�����������l���ɗ��r���č쐬���ꂽ���̂ŁA���̓_�������@�ʒB�Ƃ����܂��B�u�f�f���v�́A��t�����҂̎��Â��ǂ��i�߂邩���f���邽�߂ɕt��������̂ł����āA�Ɩ���O�̔��f��Ɏg�����̂ł͂���܂���B�g���Ă͂����Ȃ����̂ł��B�Ƃ��낪�r��Q�E�u���s�o���nj�Q�v�Ɛf�f���ꂽ��Ў҂��J�А\�����N�����ƁA���炩�ɉߏd�Ɣ��f�����J�������̉��ł̔��a�ł����Ă��A���̔F�����ӂ邢�����̓���ɂ��ċƖ��O���肪�o����Ă��܂��B�����āA���ɂł͋��s�{�E�J�́u�����J�Ѝٔ��v�ō������s�i���A������ĔF�������������܂ł́A�u�ŊԔw���j���v������Ɛf�f���ꂽ��Ў҂̘J�ДF��́u�Ɩ��O�v�Ƃ���Ă��܂����B�ߘJ���ł��N�������o���ŖS���Ȃ����ꍇ�A�ŏ��f���E��b���a�ɂ����̂Ƃ��āu�Ɩ��O�v�Ƃ���Ă��܂������A��w�I�������܂ߓ����̐ςݏd�˂̒�����u�Ɩ���v�Ƌ~�ς����悤�ɂȂ�܂����B
�@�u���s�o���nj�Q�v���L��l�̘J�Е⏞���S�����l�̂��Ƃ������܂��B�����A���ɋ��s�o���nj�Q�����݂����Ƃ��Ă��A�ߏd�J���ɂ��炳���O�͒ɂ݂���ɂ����݂������N�l�Ƃ��Đ������J���ł��Ă����l���A�Ɩ��������ŕa�C�ɂȂ莡�Â�x�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ���A�J�АE�ƕa�Ƃ��ċ~�ς����̂����R������ł��B�܂��Ă�{�l�̑f���E�̎��ɖ�肪����̂ł͂Ȃ��A�Ɩ����S�ɂ���ċ��s�o���nj�Q�����ǂ��鎖������Ƃ̌������\�����݂��鍡���A�J���ی�s���̐ӔC�ɂ����đ��}�Ɍ�����[�߂Ă������Ƃ����߂��Ă���ƌ����܂��B�i���̌�́u���65���v�ʒB�����l�̖��_������Ă���A��ŐG���̕ʔF���̂Ƃ���ŁA��̓I�ɖ��_�����܂��B�j
�@����ɁA�����r��Q�̘J�ДF��������ĕs���ȋƖ��O�����s���Ă��鎞�������炱�������čl���Ă������������ꕶ���Љ�܂��B
�@����͉ߘJ���̘J�ДF��������čٔ��i�n�فE���فE�ō��فj�ō����̔s�i�������A�F���̍��{�I���������Љ�I���ɂȂ����Ƃ��A�����̘J���ȔF��������������e���̘J�ДF������ӔC�ғ����W�߂čs������c�ł̍��̐������e�ł��B
|
|
|
| �@�Ɩ��㎾�a�F������S���҉�c�@�������������������V�D�Q�D�W |
 |
| �@�P ��c�̎�| |
 |
| (1) |
�V�F���̓��e�A�l�����ɂ��āA�����A�\���ȗ��������Ă����������߂̂��̂ł��邱�ƁB |
|
 |
| (2) |
���ɁA�F��̎p���ɂ��ẮA�ʒB�������ł͏\����������ɂ������Ƃ���A��c�Ő������邱�ƂƂ������̂ł��邱�ƁB |
|
 |
| �@�Q�@�F�������̔w�i |
 |
| (1) |
�]�E�S�������̘J�ДF��Ɋւ���ᔻ
�]�E�S�������̘J�ДF��Ɋւ��ẮA���a62�N�̔F��������������A�l�X�Ȕᔻ���������B�Ⴆ�A |
|
 |
|
�@ |
�Ɩ��̉ߏd���̕]���ɓ�����A���ǑO�P�T�Ԃ܂ł��d�������ɂ́A�������Ȃ��B |
|
 |
�A |
���ǑO�P�T�Ԉȓ��ɋx��������ꍇ�A�Ɩ��O�Ƃ����B |
|
 |
�B |
�F���́A�؎̂Ċ�ƂȂ��Ă���B |
|
 |
�C |
�������̂Ȃ��ɔ��ǂ����l�����Ȃ���A�F�肳��Ȃ��Ƃ����戵���͂��������B
�Ȃǂł���B |
|
|
 |
|
�܂��A�ŋ߂̍ٔ���̂Ȃ��ɂ́A |
|
 |
|
�@ |
�Ɩ����ߏd�ł��������ۂ��́A���ǂ����{�l�ɂƂ��ĉߏd�ł���Ώ\���ł���A����ɓ������ɂƂ��Ă��ߏd�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����͑Ó��ł͂Ȃ��B |
|
 |
�A |
�����̌������������Ă���ꍇ�A�Ɩ��������̈�ł���A�Ɩ���ƔF�肷�ׂ��ł���B |
|
 |
�B |
�g�p�҂����N�f�f�������Ȃ��ȂǁA�J���҂̌��N�ɒ��ӂ�Ȃ�������@�@���ɂ́A�Ɩ���Ƃ��ׂ��ł���B |
|
 |
�C |
��b�����̂Ȃ����N�ȘJ���҂�z�肵�āA�Ɩ��̉ߏd���f����Ƃ����戵���͑Ó��ł͂Ȃ��B |
|
|
 |
|
�Ȃǂ̔��|��������B |
|
 |
(2) |
�v���W�F�N�g�ψ����݂��Č������s������| |
|
 |
|
�J�ДF����߂���ᔻ�̂Ȃ��ɂ́A |
|
 |
|
�@ |
�F������������Ă��Ȃ��Ǝv������� |
|
 |
�A |
�J�Еی����x����������Ă��Ȃ��Ǝv������� |
|
 |
�B |
�]�E�S�������Ɋւ����w�I��������������Ă��Ȃ��Ǝv������� |
|
|
 |
|
�ȂǁA��Ƃ��Ĕᔻ���鑤�̗���s���ɂ����̂��������A�ˑR�Ƃ��āA�l�X�Ȉӌ�����_���w�E����ٔ��Ⴊ�U�������Ƃ�������������ƁA�Љ��ʂ̔F���Ɓ@�@�@�J�ДF��̊J�������邱�Ƃ͊m���ł���B
�@�s���́A�Љ�̗���ɓK�ɑΉ����Ă������Ƃ����߂�����̂ł���̂ŁA���܂ł��u��X�͐������v�Ƃ����ĕ��u����킯�ɂ͂����Ȃ��B ���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���̊J�������ɂ����̂��A�܂��A�ǂ̂悤�ɂ���Ζ��߂��邩���A�����Ɍ������邽�߁A�v���W�F�N�g�ψ����݂������̂ł���B
�@�v���W�F�N�g�ψ���ł́A�J�ДF����߂�����_�����A����̑Ή��̂���������܂Ƃ߂����A���̓x�̔F���̉����́A���̌������ʂ��čs�������̂ł���B
�@�Ȃ��A���̓x�̉����ł́A�^�p�̉����̂ق��ɁA�F�������������������悤�ɂƂ����z������A�X�������̊�Ƃ��ēǂ݂₷������ƂƂ��ɁA�d�v�ȍ��ڂɂ��ẮA�ł��邾���ڂ��������������邱�ƂƂ������̂ł���B |
|
 |
| �@�R�@�F��̎p�� |
 |
�@�]�E�S�������́A��w�I�ɂ����𖾂ȕ����������A�F���ɂ����Ă���̓I�Ȏړx���������Ƃ��ł��Ȃ����߁A�J�ДF��ɂ����āA�F��S���҂̎p�������_�ɉe�����y�ڂ��\��������B
�@�F��S���҂����ӓI�ɔ��f����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�ǂ̂悤�ȐS�\���ŔF�莖���ɓ����邩�ɂ���Č��ʂɈႢ���o�Ă���Ƃ������Ƃł���B |
 |
(1) |
��{�I�Ȏp�� |
|
 |
|
�C |
�@�s���ł��邱��
�@�J�ДF��́A�J���s���̈�ł���B�s���ł���ȏ�A�����̂��߂ł���K�v������A�����Ɏx������邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�܂��A�s���́A�Љ�̕ω��ɓK�ɑΉ����邱�Ƃ����߂���B�s���̑��ɂ������肵���l�����������Ƃ��Ă��A�����̎Љ�Ƃ̊Ԃɑ傫�Ȋu���肪����Ƃ���A�s���Ƃ��āA�ǂ����ɖ�肪����ƍl����ׂ��ł���B
�@�K�ɑΉ����邱�Ƃ��d�v�ł����āA�l�X�Ȉӌ���ᔻ�����Ɏ����Ηǂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�@�ӌ���ᔻ�������Ƃ��Ȃ��̂ł���A�����������čs�����A����Ɋ�Â����̂�ꕔ�̈ӌ��ł����ĎЉ��ʂ̈ӌ��Ƃ͔F�߂��Ȃ����̂ɂ��ẮA�s���̍l�������ǂ����������悤�ɓw�͂��ׂ��ł���B
�@���̓x�A�v���W�F�N�g�ψ���Ō������s���A�F�������������̂́A���̂悤�ȍl���ɂ����̂ł���B |
|
 |
�� |
�@�@�߂Ɋ�Â��čs���ׂ��ł��邱��
�@�J�ДF��́A��̓I�ЊQ����ɂ��Ė@�߂����߂��K�p�����Ƃł���B�����܂ł��A�@�߂������Ƃ��A�@�߂Ɋ�Â������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ́A�F���Ƃ̊W�ŏd�v�ȃ|�C���g�ł���B
�@�F���́A����ɊY��������̂́A���i�̎���Ȃ�����A�Ɩ���ƔF�肵�Ă悢�Ƃ������̂ł���B
�@���������āA�F���ɊY��������̂́A�Ɩ���Ɛ���ł��邪�A�F���ɊY�����Ȃ����̂��A�����ɋƖ��O�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�@�v����ɁA�J�ДF��́A�F���ɊY�����邩�ǂ����f���邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�@�߂̗v���ɊY�����邩�ǂ����f���邱�Ƃ��ړI�ł���B
�@�F���͐؎̂Ċ�ƂȂ��Ă���Ƃ����ᔻ�͂������琶���Ă���B�F���ɂ͊Y�����Ȃ����A�Ɩ���ƍl������Ƃ����������Ƃ��́A�K�v�ɉ����{�ȂƂ����k�̏�A�T�d�ɑΉ����ꂽ���B |
|
|
 |
(2) |
���f�ɖ����ꍇ�̑Ή��̎p�� |
|
 |
|
�C |
�@�F������̓I�łȂ����߁A�Ɩ���E�O������Ƃ��m�M�����ĂȂ��ꍇ
�@�]�E�S�������̘J�ДF��̓���́A���ɂ��̓_�ɂ���B�����Ƌ�̓I�Ȕ��f��������ׂ��ł���Ƃ����ӌ������邪�A���݁A��w�I�ɕ������Ă������ł́A����ȏ�̊���������Ƃ͕s�\�ł���B
�@�F�����Ȃ��A�D�F�������傫�����A�F��̍l������ǂ��������A�F�莖��Ȃǂ��Q�l�ɂ��āA�Ó��Ȑ������o������ŁA�F��S���ҁi�ē����j�̍ٗʂ͈̔͂ƔF�����A���肵�Ă������������B
�@������Ȃ�����Ƃ����ĕ��u���邱�Ƃ͋����ꂸ�A�Ɩ��ォ�O�����f����`��������B�������A�������ɂ��ẮA�{�Ȃ��ꏏ�Ɍ�������̂ŁA���k�A���c�A���f�ȂǘA�g�����肢����B |
|
 |
| �� |
�@�NJǓ��ɔF�莖�Ⴊ�Ȃ��ꍇ
�@�X���̔F�莖�Ⴊ�S���Ȃ�����Ƃ����ē��ɖ�肪����Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�F���̍l�����A���ɋƖ��̉ߏd���ɂ��Ă̗��������ǂƔ�r���Č���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����ڂŁA�F�莖��̎Q�ƁA���ǂƂ̈ӌ������A�ʎ��Ăɂ��Ă̖{�ȂƂ̈ӌ������A�Lj�Ƃ̈ӌ���������ʂ��āA�F�肪�K���ł��邱�Ƃ��m�F���Ă݂邱�Ƃ��K�v�ł���B |
|
 |
�n |
�Ǔ���1���̔F�莖��ƂȂ�ꍇ
�Ɩ��ォ�ۂ��́A�NJǓ��ɔF�莖�Ⴊ���邩�ۂ��Ƃ͖��W�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B �������Ȃ���A�����ɂ́A�F��S���҂Ƃ��ẮA�Ǔ���P����F�肷��ƂȂ�ƁA�F�X�Ȃ��Ƃ��l�����S�O���邱�Ƃ��l������B
���̂悤�ȏꍇ�ł����Ă��A�Ɩ���͋Ɩ���A�Ɩ��O�͋Ɩ��O�Ƃ����W�X�Ƃ����p������ł���B |
|
 |
�j |
�@���f�ɖ����Ă���Ԃɒ����������ƂȂ����ꍇ
�@�K�v�ɉ����A�ǁE�{�Ȃɑ��k���āA�������f���ׂ��ł���B�Ɩ��O�Ƃ����ꍇ�ł��A�s���R�����x�ɂ���ċ~�ς����]�n������Ƃ������Ղȍl���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B |
|
|
 |
| (1) |
���̑� |
|
 |
|
�C |
�{���̉�c���e�ɂ��āA���̔F������S���҂ɏ\���`���悤�ɂ��ꂽ���B |
|
 |
�� |
�Lj�ɑ��ẮA����̉����̓��e�A�l�����̐������e�ǂɂ����ď\���s��ꂽ���B |
|
|
|
|
| �r��Q�̘J�ДF���̕ϑJ |
 |
�@��ɂӂꂽ�悤���r��Q�̘J�ДF���́A�ŏ��̐�����܂߂���܂łS�x��������^�p����Ă��܂����B�ŏ��̐���Ɏ���o�߂��܂߁A�F���̉���i�܉^�p�j�ɂ͂��ꂼ��傫�ȈӖ�������A�q���肪����܂��B�����A���Y�̎��a�Ɋւ��F�蓬���̌����������̂��F���ƂȂ��Ă���ƍl���ėǂ��Ǝv���̂ł��B�ǂ�Ȑ[���Ȍ��N��Q�ł��A�Љ�I�ɔF�m����Ȃ�����~�ϑΏۂƂȂ�܂���B�܂��Ă�F������点����A����������ɂ͈�w�I�ȃR���Z���T�X�������Ă��邩�ۂ������̏d�v�Ȕ��f��ƂȂ��Ă���̂ŁA����������铬�����\�z���ꂽ���ǂ������d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�S�x�ɘj��F���̉���i�܉^�p�j���A���ꂼ��ǂ̂悤�Ȏ���w�i�����Ɏ��{���ꂽ�������Ă������Ƃ́A����̔F���̉����Ɛ������^�p�����ɔ����Ă�����Ŗ𗧂��̂Ǝv���܂��B |
 |
| �P�A���a39�N�Q���u�L�[�p���`���[���̎�w�𒆐S�Ƃ������a�̋Ɩ���O�F���ɂ��āv�i���1085���j |
 |
�@���a35�N�ȍ~�R���s���[�^�[�����ɂ�鎖���������̋}���Ȑi�s���A�E��ɂ�����J���̕ω��������炵�V���Ȍ��N�j��������N�����܂����B�������A�����͂�����ƑΉ��ł����Â��Ȃ��g�F�≊�ł͂��邪�A���������̑i�����₽�瑽���̂́A�{�l���m�C���[�[�ɂȂ��Ă��邽�߂Ő��_�I�ɂ��������̂��B�h�Ƃ�����Â��ЁA���͂̌����̒��łǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��ꂵ�݂ɂԂ�����A���E�҂܂ŏo���Ɏ���܂����B���ꂪ���a37�N�̂��ƂŁA�}�X�R�~���u�L�[�p���`���[�̐V�����E�ƕa�v�Ƃ��ĕ���悤�ɂȂ�܂����B���̂悤�ȎЉ�I�������ł��Ȃ��Ȃ����J���Ȃ́A���a38�N�Ɂu�L�[�p���`���[�̘J�ДF�����Ɖ�c�v��ݒu���������n�߂܂����B���]�E�����J�A���u�L�[�p���`���[���A����c�v��ݒu���A���{�ɗv�������o���܂����B�����������ŏ��a39�N�Ɂu�L�[�p���`���[��ƊǗ���v�Ɓu�Ɩ���O�̔F���v���1085�����o����邱�ƂɂȂ�܂��B�������A���̎���
�@�@�p���`��Ƃɔ������a�Ƃ��āu�L�[�p���`���[�a�v�Ƃ��ċ��������A��Ƃ̓p���`��ƁA�������F�≊�݂̂Ɍ���A�u���炢�炵�₷���v�u�ڂ����₷���v�u���E�w���E�r�Ȃǂ̃R����ɂ݁v�͖�������܂����B |
 |
| �Q�A���a44�N10���u�L�[�p���`���[����w��ƂɊ�Â����a�̋Ɩ���O�̔F���Ɂ@���āv�i���723���j |
 |
�@�l���炵�u�������v�̐i�W�ɔ����E�Ɛ��r��Q�͂܂��܂������̎Y�ƕ���E�E��ɍL�����Ă����A�L�[�p���`���[����^�C�s�X�g�A�d�b�����肩���ʎ����A�R���x�A�[��ƁA�ە�E�E�E�ɐ[���Ȍ��N��Q�������炵�܂����B
�@�������o�c�҂����́u���Ȃ��͎w��ŃL�[��@���悤�Ȏd���͂��Ă��Ȃ��̂�����A�E�ƕa�ɂȂ�͂����Ȃ��v�u�F�≊�͘J�ЂƔF�߂�悤�����Ă��邪�A���Ȃ��̂���E���̒ɂ݂�����̎��ɂ����̂��B�v�u���̒�߂���ƊǗ���ȉ��̎d�����������Ă��Ȃ��̂����炻�������a�C�͔������Ȃ��B�v�Ƃ����āA�⏞�����ۂ��铹��ɁA���̔F�������p����悤�ɂȂ�܂����B
�@����ȏ�䖝�ł��Ȃ��Ə��a40�N�ɑS���ۂ̕w�l�������S�ɂȂ��āu�����E�ΘA�v�Â��肪�X�^�[�g�A���a42�N�Q���Ɋ�Ƃ̘g�����ŏ��̌𗬏W��J�Â���܂����B�����ɉߘJ�����ɂ̓�����W�J���Ă����`�f�r�J�g��V���J�A�������A�����s�ɐE�ƕa��{��i���a43�N�Ɂu�E�ƕa��������v100���~�\�Z���A�Ȍ�R�N�ɂ킽���ĘJ���Ȋw�������ɐE�ƕa�̗\�h�Ƒ�̒������˗����ꂽ�j�����{�����邱�Ƃ����܂����B�@�����g�́A�Ȃ̐E�ƕa�F�蓬���œ����E�ΘA������I�ɊJ�Â��Ă����u���ጟ����v��u�Ǘጟ����v�ŁA�r��Q�E���ɏǂ̕a���̗�����J�ДF�蓬���̃C���n�������܂������A��c��̋������ł̒k�����������v���o����܂��B
�@���a39�N��i���1085���j�́A�L�[�p���`���[���F�≊�Ƃ��������g���͂߂����߁A�F�肩��͂ݏo�����������V���Ɏn�܂�܂����B�˔j�����J�����̂́A���É��ŋ����Ђ̃^�C�s�X�g��������������ł����B��������͖��É���w�̎R�c�M��搶����u�r�nj�Q�v�Ɛf�f����J�А\�����܂������A�J����ē����J����ǂ���������̏Ǐ���A���A�r�̏�Q���������߁u���画�f�ł��Ȃ��v�Ƃ��Ė{���g�f�ƂȂ�܂����B�����Łu�������������v����������A�J���Ȃɒ��ڌ���������钆�ŋƖ���ƔF�肳��܂����B���a42�N10���ɂ́A�����M�p���ɂň�ʎ����E�ł��������r�ܘJ����r�nj�Q�ŘJ�А\���B�J��͓����ǂ��g�f���܂�����43�N�T���ɘJ�ЂƔF�肵�܂����B
�@�����ɗ����オ������Ў҂��x������^�����A���g�݂Ɍ��W������Â�@���̃G�L�X�p�[�g�E�J���g�����������ݑS���K�͂̓����ɔ��W����̂Ɏ��Ԃ͊|����܂���ł����B
�@���a42�N�S�����Z�������A�u�E�ƕa�ɊS�����S�Ă̒��Ԃ��S���E�S�Y�Ƃ̋K�͂ŏW�܂�A�𗬂��邽�߂̎��s�ψ���������������v�ƌĂт��������ʁA�V���J�A�A�����J�A�A�S�_���J�A�A�����J�A�A�S�A�Ȃ�27�̘J���g�����^����\�����A����ɑS������A�A�V���{��t����������s�ψ����������܂����B
�@��P��E�ƕa�S���𗬏W��͏��a42�N�X���ǔ������h�ŊJ�Â���A35�s���{������502�����Q���B��ʂɂ́u�܂̏W��v�ƌĂ�Ă��܂����A���̏W��ɎQ�������l���������ꂼ��E���n��ɋA���ĕW����J���w�o�������H���Ă����܂����B���̌��ʁA�F���ɓ��Ă͂܂�Ȃ��E���a���ł����Ă��Ɩ��������ɉߏd�ł��������A���N��Q���N�����Ă��s�v�c�łȂ����������A�J���Ǝ��a�̈��ʊW�𗝉������邱�Ƃɂ��e�n�ŘJ�ЂƔF�肳��鎖�ԂƂȂ�܂����B���Ԃ��d�������J���Ȃ́u��r�nj�Q�Ɋւ���Ɩ��㎾�a�̔F���v���쐬����u���Ɖ�c�v��ݒu���A�����Ċe�n�ɐ\������Ă���J�А\�����u��r�nj�Q�ŔF��\�������Ă�����̂ɂ��ẮA�e���Ǝ��ŔF�肹�����ׂĖ{�Ȃɏ�\����v�Ƃ����ʒB���o���܂����B
�@�J���ґ����A�U���������Ă��钆�ŏo���ꂽ�̂����723���ʒB�������킯�ł��B���I�ɂ́A���a44�N10���ɍȂ����a�����ʼn��ق���F�蓬����]�V�Ȃ����ꂽ���ŁA�E�ƕa�S���𗬏W����s�ψ�����ǒ��̕��c�厡�Y���ɘJ���Ȃ܂ŐV�ʒB�̎��ɓ��s���������A�F�蓬���̌�w���������Ƃ����������v���o����܂��B
�@������t���ł͏��߂Ă̐E�ƕa�����ŁA�J���s���݂̂Ȃ炸�J���g������ÁE�@���̐��Ƃ��J�ДF�肪�ǂ̂悤�ɐi�߂���ׂ����̂Ȃ̂��N��l����Ȃ���ł����B�U������ɋƖ��O���肪�o����A���̌�Q�N�]�̐R�������̓������o�ċƖ���ƔF�肳���鎖���o���܂����B�F�����S���I�����̐��ʂf�����P���ꂽ�Ƃ��Ă��A���̔F�蓬���ɋ�̓I�Ɋ������Ă������߂̎��g�݂��s�݂��ƁA��Ў҂͌��Nj~�ς���Ȃ��Ƃ������Ƃ��������܂����B���V�Q�R���ʒB�̓����́A
�@ ���߂Ď�w�̏Ǐ��łȂ���E���E�r�̏Ǐ���Ɩ��㎾�a�ɉ����A�܂��L�[�p���`���[�Ɩ������łȂ���w��Ƃ̏]���҂ɂ��J�Е⏞�̘g���L���܂����B
�A ������u������v���̏Ǐ�́A����݂̂ł͋Ɩ���̎��a�Ƃ��ĕ⏞�̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��B�������A�u������v�̒i�K�ɂ����āA�K�ȍ�ƊǗ��i���Ǘ��\���ɗ�[�̓K�ȏ��u�A���k�A�E��]�����܂ށj�A�x�{�A�P�����̑[�u���u���邱�Ƃɂ�����������̂��A����̑[�u���s���Ȃ��܂܍�Ƃ��p�����邱�Ƃɂ���āA�a�I��Ԃɐi�s����Ⴊ���Ȃ��Ȃ��B�c�Ƃ��ĘJ�������̉e�����l������悤�ɂ��܂����B
�B ���a�̖{�̂����ł��邩�𖾂炩�ɂ��Ȃ��ŁA�ꕔ�̐��`�O�Ȃ̐���̌o���ƈӌ��@�����Ƃɂ���ꂽ���̂ł��������߁A�ŊԔw���j�A�A�Ίp�؏nj�Q���̎����������A�����̎������啔�����J���ߒ��ŋN���肤����̂Ȃ̂ɁA���O��Ƃ��܂����B
�C �F��ɓ������ẮA����ɂ���ďڍׂɔc�����ꂽ�Ǐ�y�я�������ɍs�����ƁB
�@�Ƃ������߁A�e�n�ŘJ�Еa�@���ւ̗��\�Ȏ�f���߂���������A�[���Ȕ�Ў҂����߂Ɂ@����݂��܂����B |
 |
| �R�A���a50�N�Q���u�L�[�p���`���[���̏㎈��ƂɊ�Â����a�̋Ɩ���O�̔F���v�i���59���j |
 |
�@���ɖ��炩�ɂ����悤�ɁA�u�F���v�̑�������ЎҁE�J���҂̓����̌��ʁA������������]�V�Ȃ�����Č�ǂ��ŏo�����Ƃ������i��A�x�X�g�̂��̂͊��҂ł��܂��A����܂ŏo���ꂽ�J�ДF���̒��ŁA�ł������ȕ��ނɓ���F����59���ʒB�ł��B
�@�u723���ʒB�v���A�������̖����������Ȃ�����A��Ў҂�擪�ɁA��ÊW�ҁA�@���ƁA�w�ҁA�J���g���L�����W���������̐��ʂ̉�������ŏo���������Ƃ͂��̌�̘J�ДF��Ґ��̋}���ɒ[�I�Ɍ���܂����B�����A�u723���ʒB�v�O���N10���ʂł��������̂��A���̌�͔{�X�ő������S���F�肳���悤�ɂȂ����̂ł��B
�@���������J�ДF�蓬���̑O�i�́A���ʁA�җ�Ȑ����Ŕ����U�������܂��Ă��܂����B�����A���o�A�̒S���҂́A�u723���ʒB�v�̂悤�Ȃ�����ȒʒB���܂���ʂ�ƁA���̂����Ɍ�����⍘�ɂ̕w�l�������A�݂�ȐE�ƕa�ƔF�肳��A�����Ȃ��̂ɋ����������⏞�����B���{�̕w�l�J���҂̉ߔ��������������A���ɐ�߂���悤�ɂȂ�Ƃ����Ċ�@����������A�����Ԃ����n�߂܂����B���̐擪�ɗ������̂����ƂƂ��Ă͍ł��������r���҂�����Ă����̂��d�d���Ђł����B�i���a55�N�S�d�ʂ̔��\�ł́A�Ɩ���756���A�Ɩ��O1680���A�ۗ�42���܂߂ĔF��\����2478���A���Ґ��͎����Ҋ܂߂�7266���B�j
�@���a49�N�Q���ɓd�d���Ђ́u�r�nj�Q�v���W�F�N�g�E�`�[���v�i���M�a�@��t28���E��\�Ҋ֓����M�a�@���V�蔎���j�́A���ǂ̗v�����@��Ƃ̎Љ�I�d�v���ɋ^�O������҇A�l�ԊW�ŏ�i�ɕs�M�������҇B��Ƌ@����Ɗ��ɕs�������ҁE�E�E�G�̎��A���i�ɖ�肪����A�_�o�ǓI�X����L����ҁE�E�E�Ƃ��铚�\���o���܂����B���̓��\�͒N���݂Ă����ǂ̌����ƌ��ʂ��������܂ɂ��āu�������͔��M�҂ɑ����v�Ƃ����_����W�J�������̂ł����B���59���ʒB�́A���̖��̑����d�d���Ёu�r�nj�Q�v���W�F�N�g�E�`�[���v�̓��\��w�ǂ��̂܂����`�ŏo���ꂽ���̂ł����B
�@���̓d�d���Ёu�r�nj�Q�v���W�F�N�g�E�`�[���v�ƕ����59���ʒB�Ɉ���������S�킹���̂��A���{��ȑ�w���`�O�ȏ������i�����j�E�Γc�����ł����B�Γc�����͊��59���ʒB�̍���̂��ߘJ���ȁi�������J���ȁj���ݒu�����u�������r�nj�Q�̋Ɩ���O�̔F���ɂ��Ă̐��ƈψ���v�Œ��S�I�������ʂ����A���̎��̂��Ƃ�ǐS�I�ȉƒ�G���Ƃ��Ē�]�̂���u��炵�̎蒟�v�Ƃ����G���̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@�w�Љ�ۏ�Ƃ����̂��������K�p�����Ȃ炢���̂ł����A�����ق��ɂ����݂܂��ƁA�Ȃ܂����̂�����Ă��܂��܂��B�����Ȃ��ł��������炤�A��������������������o������A����͐l�Ԃ��߂ł��ˁB�a�C�ł���ق������ł�����A����ׂ����̂�����Ȃ��B�����������Q�����������o�Ă��Ă����ł��B�x�ƔF�����A�w�c���������ɂ́A�ǂ��܂ł�E�Ƃ��炫���a�C�Ƃ���̂��̔��肪�A�Ȃ��Ȃ��ނ���������ł��ˁB����ł͍���Ƃ����̂ŁA�J���Ȃ����N�̂Q���ɐV�����F���܂蕨�ڂ��o������ł��B��҂̔��f���������܂�����ǂ��A���̑O�ɁA�N�ł��킩�镨�ڂ����ĂāA�܂��ӂ�킯�悤�Ƃ����킯�ł��B�x�i�u��炵�̎蒟�v1975�N�������|��������146�y�[�W�j�ƌ����Ă��܂��B���̍l�����́A�����J�̒��Ԃ��u�Ɩ��O�v�ƔF�肳�ꂽ�����̌o�߂ȂǂƂ��l�����킹�Ċ��59���ʒB�̔��z�Ɛ��i��[�I�ɕ\���Ă���ƌ����܂��傤�B
�@����ɐΓc���������́A�u��21����{�ЊQ��w��v�i���a48�N�j�ŁA�u�r�nj�Q�ɂ��Ĉꐮ�`�O�ȓI������v�Ƒ肵�ĕ��Ă��钆���r��Q�̔��ǂ����̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@���Ȃ킿�u���ǂ��̎Љ���ɂ����āA�����w�I�Ȑ����Ƃ����댯������͂悭�ی�A�ۏ���Ă��邪�A�����b��������A�Љ�ɍv�����Ă���Ƃ����ӎ��̏[������Ȃ����ƁA���Ƃɖ{�l�̍�ƈӗ~���傫�����E���A���Ȃ̐E���ɑ���v���ӎ��@�������ƂȂ�B�{�NJ��҂́A���ł͎d�����ʔ����Əq�ׂĂ��邪�A���̒ꗬ�ɂ́A�����̔\�͂��A�\���ɔ����ł����A�����ɑ���s���A�^�O�A��Ɏ��a�Ƃ̌��т��ɂ����āA�s���������Ă�����̂������B�܂��A�ӔC�𑼂ɓ]������X���A�˗��S�����A�����̎��a�͂��ׂĊ�����������ł���Ƃ̖��ӔC�ȌX�����ڗ��̂������ł���B���̓_����A�l�ԊW���~�����������A����͐E��݂̂Ȃ炸�A�Ƒ���F�W�ɂ����Ă����̌X�����݂�ꂽ�B���������āA����̎��Ԓ������A���`�O�ȓI�ɂ́A�p���̎w������сA��b�̗͂Â��肪�����߂��A���_�I�ɂ͌��N���̉A�ӗ~�I�ɐE���ɖv������v���ӎ������߁A��������I�Ȍ��N�f�f�ɂ��A�K�Ȍ��N�Ǘ��̐��̕K�v�����Ɋ����ꂽ�v�i�u�r�nj�Q�ɂ��ā[���`�O�ȓI������v�u���{�ЊQ��w��v��22����T���A���a49�N�T���P��372�`373�y�[�W�j�Ƃ����̂ł��B�Γc�����̎v�l�@�ƁA�d�d���Ђ́u�r�nj�Q�v���W�F�N�g�E�`�[���v�̓��\�Ƃ�����܂��ɂ߂ėގ����Ă��邱�ƂɋC�t������܂���B
�@������傫�Ȗ�肪�������̂́A�u�����ɂ����㎈��ƈȊO�̍�ƂŔ��ǂ��邱�Ƃ͈�ʂɖR�����v�Ƃ��āA�ە���r��Q��Ώۂ���O���Ă��܂������Ƃł��B
�@723���ʒB���o���ꂽ���a44�N�����A�w�l�̏A�J����ʉ����A����ɔ����g�|�X�g�̐��قǕۈ珊���h�̉^�����S���I�ɋN����܂����B�����ĕۈ珊�ɋ��߂��鎿�I�ω����Љ��f���đ傫���l�ς�肵�Ă����܂����B���̃A���o�����X�̍s�������悪�ۈ�J���҂̐[���Ȍ��N�j��ł��肻�̑�\�i���r��Q�E���ɏǂ������̂ł��B������723���ʒB�́A�ە���r��Q�̋Ɩ���O�f����F���ł͂Ȃ��������߁A�ە�̘J�А\���i�܂ތ����ЊQ�\���j�͍�����ɂ߂܂����B���̈ב����ە���r��Q�̋Ɩ���O�f����F�������悤�ɂƂ̉^�����S���I�Ɏ��g�܂�Ă��܂����B�S���J�АE�ƕa����s�ψ���̍ĎO�̗v���ɑ��J���ȁi�������J���ȁj�͌������Ɖ��Ă��܂������A���ꂪ�����ďo�Ă����̂�����59���ʒB�������̂ł��B���̓_�����59���ʒB�͋H��̈��ʒB�Ƃ����܂��B
�@723���ʒB���J���ҁE��Ўґ��̍U���̒��ŏo���ꂽ���̂Ȃ�A59���ʒB�͌o�c�ґ��̖җ�Ȋ����Ԃ��̌��ʂƂ��ďo���ꂽ���̂Ƃ����܂��B�������������́A����Ȓ��ł���Ў҂�擪�ɘJ�E�@�E��̉p�m�����W���č����̎�_���U�߂邱�ƂŁA�J�ДF��̓����J���Ă��܂����B
�@59���ʒB�̎�Ȗ��_�́A���{�Y�Ɖq���w���r��Q�������o�����v�����ɂ܂Ƃ߂��Ă���̂ł��̑S�����Љ�܂��B
�@���̗v�����́A�k�C���E�ΘA������{�Y�Ɖq���w��Ɉ�w�I���ꂩ�猟�����Ăق����Ɨv���������̂��A�P�N�Ԃ̌������o�ĘJ���ȁi�������J���ȁj�ɒ�o���ꂽ���̂ł��B�����������g�݂̌��ʂƂ��āA��q���鎖���A���S�T���͏o����܂����B����̎��g�݂ɑ傢�Ɋ������Ă����˂Ȃ�܂���B |
|
|
|
|
�����@�u�㎈��Ƃɂ��ƂÂ����a�̋Ɩ���O�̔F���v
|
|
|
|
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���{�Y�Ɖq���w���r��Q������ |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���a51�N4�� |
|
|
|
|
|
|
�@�ߔN�ɂ�����Y�Ƃ̍������A�@�B���ɔ����J���̕ω������ݏo�����V�����E�ƕa�ł����r��Q�Ȃǂ́A����ɑ����̐E��ɍL�����Ă���B�������A���̊ԑ�ɂ��Ă̎��Ə�̑�͈ˑR�Ƃ��ď\���łȂ��A�\�h�y�ѕ⏞�̑�̊�����P����邱�Ƃ���w�]�܂�Ă���B���ɗ\�h�ɂ��ẮA���K�o�^�@�y�ш��t�H��̎g�p�҂ɂ��ĒʒB���ꂽ�Ɏ~�܂��Ă���B�����A�⏞�ʂɂ��ẮA�r��Q�Ɋւ���F���̍ĉ��������a50�N�Q���ɍs��ꂽ�i�ȉ��ʒB�Ɨ����j�B�J���Ȃ̎����A���V���ɂ��ƁA����̎�ȉ����_�́A
(1)�u�r�nj�Q�v�̒�`����w�̐i�����ɉ����ĕ��Չ��������ƁB
(2)��Ƒԗl�A�E��A��Ə]�����ԁA�Ɩ��ʂɂ��Ă̔��f�����̓I�Ɏ��������ƁB
(3)�ӕʐf�f�ɗp����u�_�o���Lj����e�X�g�v�̎�Z�ƕ]���@�����������ƁB
(4)�u�r�nj�Q�v�̗×{�ɂ��Ă̈�ʓI�ȍl���������������ƁB
�ɂ���Ƃ���Ă���B
�@�����̓��e�ɂ��āA�������͏d��ȊS�������Č����������A�����ĒʒB�{�s��́i�Ɩ���O�j�F���̉^�p�̏���A���̒ʒB�Ɏ�����Ă����r��Q�̕a���̍l�����A�y�ыƖ���F��̗v���͐E��̎���ƌ����̐i���ɓK�����Ă��Ȃ��_�̑������Ƃ��w�E���ꂽ�B�ȉ��ɂ��̊ԑ�_���q�ׁA�F���y�т��̉^�p�Ɋւ��ĉ��P����邱�Ƃ�v������B
(1)�ʒB�́A�u�r�nj�Q�v�ɂ��āA�u��X�̋@���ɂ��㓪���A�z���A���b�сA��r�A�O�r�A��y�юw�̂����ꂩ���邢�͑S�̂ɂ킽��A�w����x�w���т�x�w�����݁x�Ȃǂ̕s���������ڂ��A���o�I�ɂ͓��Y�����̕a�I�ȏ��ɋy�ыْ��Ⴕ���͍d����F�߁A���ɂ͐_�o�A���njn����Ă̓����A�z���A�w���A�㎈�ɂ�����ُ튴�A�E�́A���s�s�S�Ȃǂ̏Ǐ�����������Ƃ̂���Ǐ�Q�v�ƔF�肵�Ă���B
�@�������A�킪���̑����̌����ł́A���ۂɂ�����Ă��鎾�a�́A�]���̋��ȏ��ɂ݂����r�nj�Q�̕a���Ɉ�v�����A�܂��]���̂��ꂪ�N��I�v���̉�������ލs�ϐ��I�ω��Ȃǂ���b�Ƃ��Ĕ��ǂ���ƍl���Ă���̂ɑ��A���ꂪ�F�߂��Ȃ���N���Ǝ҂ɑ������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă���B�܂��A��L�̒�`�́A�{���a���㎈����Ƃ���^����n�̏�Q�Ƃ��đ����Ă��邪�A�����̏Ǘ�́A�{���a�̓��e�́u�^����n�݂̂łȂ��A�_�o�n�i�����A�����j�A�����_�o�n�A���o��n�A�z��n�̏�Q���v�i���a48�N�x���{�Y�Ɖq���w��u�r�nj�Q�v�ψ���j���̂ł���A�u���A�����̏Ǐ܂܂�邱�Ƃ�����v�A�u�m�o��Q�̔������K�������_�o�x�z�Ɉ�v���Ȃ��v���Ƃ�F�߂Ă���B�܂��A�{�w��̕ɂ������_�o�n�̏�Q���d��������̂������Ă���B���̂悤�ɁA�{���a��P�Ȃ�^����n�̏�Q�Ƃ݂Ȃ��A�S�g�I�L����������ɂƔF�߂Ȃ��ʒB�̍l�����͎��Ԃɍ���Ȃ����̂ł���A���̎��a�̒�`�͉��������ׂ��ł���B
(2)��Ƒԗl�ɂ��āu���I�ؘJ��v�����łȂ��A�K�������A��A�w������Ԃ��g�p���Ă��邩����Ȃ��u�ÓI�ؘJ��v���܂߂����Ƃ́A�R���x�A��Ǝ҂ȂǂɏǏ������Ă��邱�Ƃ������O�i�ƕ]���ł���B�������A��Ǝ҂̘J���@���S�Ƃ��āA�u�ؘJ��v�݂̂������A���_�A�_�o�A���o��̋@�\�ɋy�ڂ����S�ɂ��ĐG��Ă��Ȃ����Ƃ͑Ó��łȂ��B
�@����ɁA�Ɩ��A���V���́A�u�����ɂ����㎈��ƈȊO�̍�ƂŔ��ǂ��邱�Ƃ͈�ʂɖR�����v�Ƃ��A�d�ǐS�g��Q���i�V�j�{�y�ѕۈ珊�ە�̏�Q�ɂ��Ă͘J����w�I�ȉ𖾂�����Ă��Ȃ��Ƃ������R����A�����I�ɂ͋Ɩ��ԗl���珜���Ă���B�����̂��Ƃ́A�w��Ȃǂ̕��N�X�����Ă���A�܂��J��������{�݂̉��P�̕K�v���F�߂��Ă��鎖���Ƃ͑S���H������Ă���A�w��I�i���ɉ����悤�Ƃ��Ă��Ȃ��ƍl����B���ɕە���ʎ�����Ǝ҂̔F��͒ʒB�{�s���ނ��Ă���悤�ɂ����݂���B�����̓_�ɂ��Ă̈�w�I���������𑣐i���A���̐��ʂ𑬂₩�ɍ̂����āA����̐E��Ŕ��ǂ��Ă��銳�҂̕⏞�𑣐i���ׂ��ł���B
(3)��Ə]�����Ԃɂ��āA�ʒB�́u��ʓI�ɂ͂U�������x�ȏ�v�Ƃ��A�u��ƕs���ꂩ�炭��P�Ȃ��J�v�������Ă���B�������A��Ƃ̋���P����K���z�u�Ȃǂ̔z�����Ȃ����߂ɁA��Ə]�����Ԃ��U���������ł��r��Q���������Ă�����Ⴊ���Ȃ��Ȃ�����ŁA���̂悤�Șg���͂߂邱�Ƃ͌��ł���B���ɁA���̂��Ƃ����𗝗R�ɂ��ċƖ��O�Ƃ��锻�肪����Ă���B�]���āA��Ɠ��e�A�J�������A�P������A��Ǝ҂̌��N�Ȃǂɉ����Ċ��Ԃɂ͕�����������ׂ��ł���B
(4)�ʒB�́A�Ɩ��N�������ؖ�����ő�̗v���Ƃ��ċƖ��ʂ������A�u����̘J���ҁv���邢�́u�P�����A1���̒ʏ�ɔ䂵�ċƖ��ʂ�������Ԃ��R�����ȏ㎝�����Ĕ��ǂ��邱�Ƃ�v���Ƃ��Ă���B
�@�������A�d�v�Ȃ��Ƃ́A��Ɣ��ǑO�̘J�����ׂ����̍�Ǝ҂ɂƂ��ĉߑ�ł��������ǂ����ł���A���l�̍�ƗʂƂ̔�r�Ŕ��肷�邱�Ƃ͑Ó��łȂ��B���ɋƖ��ʂ������ł����Ă���ƎҎ��g�̏����̍��ɂ���ĘJ�����S�̒��x���Ⴄ����ł���B�܂��A�Ɩ��ʂ̒��������ǑO�Ɍl�ɂ��čs�Ȃ��Ă��炸�A���ۂɂ͂��łɏǏ�����A���̂��߁A��Ɣ\�͂��ቺ�����i�K�Œ��ׂ��Ɩ��ʂ��r�̑ΏۂƂ��邱�Ƃ������̂ł��邩��A�L�ǎ҂ɑ��Ă��̂悤�ȗp�����ۂ��邱�Ƃ͓K���łȂ��B�ʒB�Ɏ����ꂽ�u10���A20���v�u�R�����v�Ȃǂ̊���l�́A�u���Ƃ̈ӌ����̑����Q�l�Ƃ��ď펯�I�Ȑ��Ƃ��Č��߂��v�Ɛ�������Ă��邪�A�Ȋw�I�ȗ��t����������Ă��Ȃ��B���́A������Ԃɂǂ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��d���������č�Ƃ����Ԃ�c���ł���悢���Ƃł���B�����A�l�̋Ɩ��ʂ𐳊m�ɑ��肷�邱�Ƃ͎��O�̑̐����Ȃ������ł���A���Ǝ҂���o���������́A���i�ʂȂǑ��肵�₷�����̂����Ɍ���A���l�𑨂��ɂ������̂��܂߂Ă��Ȃ����Ƃ������B
�@�Ȃ��A�����A���ɂ��ƋƖ��ʂ��c�����������Ƃ��́A���ԊO�J����x�e�A�x���̎擾�̏��画�f���č����x���Ȃ��Ƃ��Ă��邪�A���ۂ̉^�p�ɂ����Ď��ԊO�J�������Ȃ����Ƃ�N�x�𗘗p���Ă��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��ċƖ����ɖZ�łȂ��Ɣ��f����Ⴊ������Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B
�@�����̉u�w�I�������A�z���r��Q�̎�v�Ȕ����v�������܂��܂ȊO�I�����ƍ�Ǝ҂̓��I�����Ƃ̕s�ύt�Ƃ��ĂƂ炦�Ă���A�Ɩ��ʂ̑��������Ŕ��f���邱�Ƃ̓�����Ȃ����Ⴊ�������Ƃ���Ă���B�]���āA���Ǘv���Ƃ��Ă̋Ɩ��ʂ̔c���ƕ]���̕��@�ɂ��ẮA���ۂɂ͓���E����r��Q���������Ă��������߂Č�������K�v������ƍl����B
(5)�ʒB�ɂ́A�O���A��V�I��`�̂ق��W��̎��a�������āA�u�T�d�ȁv�ӕʐf�f�����߁A�W��̎��a�ɊY������u�r��Q�v�ł͂Ȃ��i�������W��̂��̂̒��ɂ͕ʓr�ɋƖ���O�̔��f��v������̂�����j�Ƃ��Ă���B�������A�����̗v�����A�]���̔F��͈̔͂����߂�\���������Ƃ͖��炩�ł���B���Ƃ��Β����N��҂ɑލs�ϐ����ǗႪ���Ȃ��Ȃ�������A�f���I�Ɍ����@�������݉����₷���ǗႪ�����邱�Ƃ���A�ӕʂ�����ł�������A�ӕʂ̗v�������邱�Ǝ��Ԃ���������f�����Ƃ������B���ɁA��L�̎��a���z���r��Q���Ɩ��O�Ɣ��肳�����Ⴊ������Ă���B���̎��a�̏Ǐ�A�����A�o�߂𒆐S�ɑ����I�A�S�̓I�ȕa���̔c�����d������ׂ��ł���A�����a�̏Ǐ�A�������Ȃ����Ƃ�K�v�����Ƃ��Ȃ��悤�A����������ׂ��ł���B
�@�Ȃ��A�ʒB�ɂ́A�ӕʐf�f�Ƃ��Đ_�o����ь��Lj����e�X�g���ڂ����������A�u�ł������f����ꂽ�e�X�g���s�Ȃ��悤�W��Ë@�ւɑ��Ďw�����邱�Ɓv�i�����A���j���q�ׂ��Ă���B
�@�������A���̕��@���Ɩ��N���̊ӕʂɕK�������𗧂��Ȃ����Ƃ͒ʒB���g���F�߂Ă���A�܂��_�o�L�W�e�X�g�̂悤�ɗL���ȃe�X�g��������邱�Ƃ����ł��낤�B
(6)�ʒB�́A�u�r�nj�Q�v�̕a�i���؋ْ��A���_�I�S���I�ْ��ɂ���āu���H�Ȃ����Œ�v����Ƃ��A�u�K�ȗ×{���s�������ނ˂R�������x�i�P�����Ȃ����R�����j�ł��̏Ǐ�͏��ނ���v����u�R�������o�߂��Ă������ɏǏy�����Ȃ��ꍇ�́v�ӕʐf�f�̑[�u���Ƃ�悤�q�ׂĂ���B
�@�������A�����Ɏ�����Ă���u�K�ȁv�×{����т��čs���Ă��Ȃ��̂�����ł���A���̂����r��Q�̊��҂ɂ͂��܂��܂ȏǓx�ƕa��������B�y�ǎ҂ł͂R�������x�ŏǏy�����Ă������x�ȏ�̏Ǘ�ł͂��Ȃ蒷���ɂ킽��x�{��n�r���e�[�V�������K�v�ł���܂������I�o�߂�H��Ǘ�͋G�߁A�V��A���������Ȃǂɂ���ďǏN�����₷�����Ƃ͎��Ԃ������Ă���B�i���a48�N�x�u�r�nj�Q�v�ψ���j�B�ނ���R�����ԓ��ꎡ�Â��p�����Ă��Ǐ�̍D�]���F�߂��Ȃ��ꍇ�A���Õ��j��ς��邱�Ƃ��]�܂����Ƃ����ׂ��ł��낤�B����ɔ����ĒʒB�̎w���́A���҂̈�Ò��f�����������ꂪ����A���ɒ����×{���҂��Ɩ��O�̈���������A����S���B�e��_�Ȉ�̐f�@�𖽗߂��ꂽ���������Ă���B���́A�K�ȗ×{���Ǐ�ɉ����āA�ǂ̒n���Y�Ƃł�����悤�Ȏ�X�̈�Â⌒�N�Ǘ��̑̐������邱�Ƃł���A���́A���̎p���͏��ɓI�ł���Ɖ]�킴������Ȃ��B
�@�]���āA���I�ɂR�����Ƃ����×{�̊��������邱�Ƃ͐������Ȃ�����łȂ��A���̋K��ɂ���Ĉ�ÂȂǂ̒��f���s����Ƃ������ďǏ����Ȃ�\��������ƍl����B
(7)���a44�N�̋��F�����A�u�Ɩ��ɂ���J����v�Ǐ������A�u�ʏ�n�߂͔�J�A������̏�Ԃŋx�{�A�P���ɂ�����v���A�u���ɑf���̂���҂ł́v�u��Â�v����i�K�ɂ܂Ői�݂���v�̂ŁA�u������̒i�K�ɂ����ēK�ȍ�ƊǗ��A�x�{�A�P���Ȃǂ̑[�u���u����v���Ƃ��q�ׂĂ����B�������A���߂�ꂽ�V�F���ł́A�u��X�̋@���ɂ��v�Ƃ����q�ׂ��A��J�Ƃ̊W�┭�ǑO�ɂ�����\�h�[�u�ɂ��Ă͑S���G��Ă��Ȃ��B�r��Q�̑�Ƃ��ẮA�����f�f�A�������Â͂������A���ǑO�ɂ�����[�u���d�v�ł��邾���ɁA���̒ʒB�͈����ނ��Ă���B
(8)�ȏ�̂悤�ɁA���̒ʒB�̓��e�͎��a�̎��Ԃƌ����̐i���ɂƂ��ċ^��̓_�������B�������A���ꂪ�F��̒n��i�����Ȃ����A��t�̈ӌ����قȂ�ꍇ�̑�Ƃ��ďo����Ă���i����ł͊�O�̏Ǘ���㕔���ւ��g�f����[�u���������̂������Ă���Ȃǁj�B���̂��Ƃ́A�ʒB���Œ��Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�ō���Ƃ��ċ@�B�I�ɉ^�p�����댯�������Ă���B�����A�����ł���A��̖ړI�ł���u�J���ҕی�v�ɂ����Ċ��҂̋Ɩ���F��ƈ�Â�i�߂邱�Ƃ��������đj�ޖ������ʂ����댯������B
�@�������́A��ɂ��������_�ɂ��ĉ��P����ƂƂ��ɁA�r��Q�̗\�h�A�⏞��̊m���ƕ��y�ɂ��ēw�͂���悤�����v��������̂ł���B |
|
|
|
|
|
|
|
�@�S���J�АE�ƕa����s�ψ���J���ȁi�������J���ȁj��59���ʒB�̉^�p���߂����ċƖ��^�c�̉��P�����s�������͎̂��̓��e�ł����D
�@�Ƃ�킯���a51�N11��11���t�ŏo���ꂽ�����A��45���́C59���ʒB�Ŕ����Ă����ەꓙ�i�㎈�ƕ����Đg�̂̑��̕��ʂ������Ɏg�p����Ɩ��ɏ]������J���ҁj���r��Q�Ɋւ��J�А\�����������ۂɂ́C�F���ɂ�邱�ƂȂ��C�ʂɍ�Ƒԗl�E�Ɩ��ʓ���c���̏�Ɩ���O�f����悤�w�����܂����D�܂��C�K�ȗ×{�⌒�N�Ǘ����s���Ȃ������ꍇ�C�R�����ŏǏ��ނ��Ȃ����Ƃ�����̂ŁC�K�ɑΉ�����悤�Ɏw�����܂����D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�����A��
�@���a�\��N�Z���\�l��
�e�s���{���J����ǘJ�Ў喱�ے��a
�z���r�nj�Q���̐E�ƕa���a�Ɋւ���{�Ȓ�ɂ���
�@���a�\��N�Z���\����A�S���J�ЁE�E�ƕa����s�ψ����A�{�Ȃɑ��Ē�E����A�v�|���L�̒ʂ艞�������̂ŁA�Q�l�܂łɂ��m�点�������܂��B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@50�E10�E13�̌��ɂ����āA59�ʒB�̂����u�����ނˎO�������x�ł��̏Ǐ�͏��ނ�����̂ƍl������v�̕\���ɂ��Ď�X���_���w�E���A�J���Ȃ́u��肪�d�v�ł���̂ő��}�Ɍ�������B��̉����o�߂́A��Ôǒ������A���Ŋe�ǂɒm�点��v�Ɩ������A�����A���͏o�������B��`�O�̋ǂŕ��������A���̂悤�ȕ����͗��Ă��Ȃ��Ƃ����Ă���B |
|
|
 |
|
|
�@�J���ȂƂ��ẮA59�ʒB���̂��̂̓��e�Ɍ�肪����Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B���ʒB�̎�|�����Ǝ傪������u�O���������Ă�����Ȃ����̂͋Ɩ���̇�������ł͂Ȃ��v�Ƃ��č��ʓI�戵�������Ă�����̂�����Ƃ���Ζ��ł���̂ŁA���}�ɂ��̑����������Ɠ����Ă���B���̌o�߂�50�10�14�t����Ôǒ�������Ŋe�ǂɎ����A�������B�܂�59�ʒB�̎�|�ɂ��Ă͑S����c�Ő������Ă���B |
|
 |
|
|
�@�����͂ǂ̂悤�ɂ����̂��A�܂��A�Y�Ɖq���w��̌����59�ʒB�̖��_���w�E���A�J���ȂɔF���̉�����v���������A����ɂǂ��Ή��������B |
|
 |
|
|
�@�J���Ȃɂ����Ă͌���10�ȏ�̐��Ɖ�c��݂��A�R�ς�����̉𖾂Ɏ�g�ނƓ����ɐV�����F���̐ݒ�ɓw�͂��Ă���B����������y�����Ă����ł͂Ȃ����A�����I�Ɏ肪��肩�˂Ă���̂�����ł���B���炭���Ԃ�݂��Ăق����B�i���Ɖ�c�̎�����������B50�E10�E14�̓�����������Ăق������̂��Ƃ肪����A���ɊJ�Ò��̓���c�̐R�c���������ƂƂ���50�E10�E14�������N�ǂ����B) |
|
 |
|
|
�@������A�ǂ̂悤�Ȏ菇�Ō�������̂����炩�ɂ���B |
|
 |
|
|
�@�u�r�nj�Q�̔F���̌����Ɋւ�����Ɖ�c�v�����W����N���̒�̗v�|�A�Y�Պw������̗v������A��w�I�Ȗʂ��猟�����Ē������Ƃ��l���Ă��邪�A���̎����́A������������������˂�B |
|
 |
|
|
�@�����ɒ��肵�Ă��A���̌��_���o��܂łɂ͎��Ԃ������邵�A�܂��Č����ɂ������Ă��Ȃ��Ȃ��ŁA��Ў҂ɋ]���҂��o�Ă����u���Ă����Ƃ������Ƃ��B���ɎO�������������_�Ŋӕʐf�f�����v���A�܂��J�А������������ɎГ��⏞���Ă����Ƃł́A���̎������������ꂽ�Ƃ��āA�⏞�Ő�A���ٓ��̌��O���o�Ă���B |
|
 |
|
|
�@�F����̏��ɂ��̂悤�ȏ����A59�ʒB�ɂ���ޕ��Q�̎��Ԃ�����Ȃ�A�ē��ɖ{�l�����k�ɗ��Ăق����B�ē��ɂ����ē��Y���Ǝ�ɑ��ĕ��Q�����̂��߂̍s���w�����s�Ȃ��B���������Q�̔F�����ق��Ă͍���̂ŔO�������Ă����������A�ĕʐf�f���s�����Ƃ܂ŕ��Q���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�ĕʐf�f�͗Տ���ł���A����s���Ă��邱�ƂŁA�a����c�����A�K���Ȏ��Â��s�����߂ɂ͕K�v�ł���ƍl���Ă���B |
|
|
 |
|
|
�@���k�ɗ����X�̖��ɂ��čs���w�����s���Ƃ������Ƃł͍���B���k�ɍs�����Ƃ��m�炸�����Q���肷��҂��o�邩�燀��������҂��o�����S���Ǝ���W�߂Ď�|�̓O���}��ׂ����B |
|
|
 |
|
|
�@�ē��̎�̓I�\�̖͂�������A�܂��A�S���Ǝ傪59�ʒB��������A��Q�҂̍��ʓI�戵�����s���Ƃ��������ł���Εʂ������̂悤�Ȉӎ��������Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ��҂��W�߂Ďw������Ƃ������Ƃ́A�����Ċ�قȊ�����^���邱�ƂƂȂ�̂ŁA�S���Ǝ��ΏۂƂ���s���w���͍l���Ă��Ȃ��B |
|
|
 |
|
|
�@�ە�̇�������@�̖��͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�B�J���Ȃ͐��N�O���猟����Ă��邪�A�����_���o��̂��B����ǂ�����̂��B |
|
 |
|
|
�@�ە�̋Ɩ��ɂ��ẮA��w��Ƃ̎��ԂƂ͈ق����ԗl�����肻�̋Ɩ��Ƈ���������ǂƂ̊W���K���������m�łȂ��̂�59�ʒB��K�p������������������Ƃ��Ă���B�J���Ȃ̈ϑ������̌��ʁA���O�������������Ƃ��āA���Ɖ�c�Ɍ������肤���Ƃ�\�肵�Ă���B |
|
 |
|
|
�@�ϑ��������ʂ͌��\���čL���Ȋw�I�ȓ��c�̏��^����ׂ��ł͂Ȃ����B |
|
|
 |
|
|
�@�������ʂ͐��Ɖ�c�ɒ�o���A���������ɂ��铙�s���ʂŊ��p���Ă���B�������ʂ͌����҂̌l�̗�������l������ʂɌ��J���Ă��Ȃ����A�����҂̊�]�܂��͗����������ĕK�v�Ȃ��̂͘J���Ȃ̊��s���ɏW�^���A���m��}���Ă���B�܂��A�����҂����̋@��Ɋw��I�ɔ��\�������Ƃ������Ƃł���A����𐧖Ă��Ȃ��B |
|
 |
|
|
�@�����҂̗������Ȃ���Ό��J���Ȃ��̂��B���Ȓ��ł͌��J���Ă���B����ňϑ������������͍̂����Ɍ��J���A�Ҍ�����`��������B |
|
 |
|
|
�@�����ł��Ȃ��B�����ۑ�Ƃ���B |
|
|
|
|
�����A��
�@���a�\��N�㌎�\�l��
�e�s���{���J����ǘJ�Ў喱�ے��a
�S���J�АE�ƕa����s�ψ���̗v���ɂ���
�@���a�\��N�㌎�\�O���A�W�L�c�̂���u�r�nj�Q�v�@�i���a�\�N�ܓ��t���59���j�@�̒ʒB�̂����A�u�O�J���ł��̏Ǐ�͏��߂���c�c�v�@�̉��߂ɂ��Ă͍ĎO�̗v���ɂ�������炸�ē��܂Ŏ��m����Ă��Ȃ��Ƃ̗v��������A��N�\���\�l���t�A�{�N�Z���\�l���t�̈�Ôǒ������A���@�i�ʓY�j����Ă���܂��̂Ō䗹���肢�܂��B
|
|
|
 |
|
�����A���@��45��
���a51�N11��11��
|
|
|
�@�@�@��@�@���@�@�ہ@�@��
�s���{���J�����
�J �� �� �� �� �� �a
�U����Q�̔F�����̉^�p��̗��ӓ_�ɂ���
�@�E�Ɛ����a�̋Ɩ���O�̔F���̉^�p���Ɋւ��鎿�^�ɂ��ẮC���̓s�x�������Ă����Ƃ���ł��邪�C���̗v�_�����L�̂Ƃ���Ƃ�܂Ƃ߂��̂ŁE�Ɩ��̎Q�l�Ƃ���ق��C�K�v�ɉ����W�J�g�y�ш�t�ւ̎��m�������L���Ƃ�͂����ꂽ���B
�P�D�U����Q�i���j
�Q�D�r�nj�Q
(1)�Ɩ��ɋN������z���r�nj�Q�̔����̋@���͈�w�I�ɕK���������m�ɂ���Ă��Ȃ����C��ʂɈ��̍�Ǝp�����������C�g�̂̈ꕔ�i��Ƃ��ď㎈�j�݂̂��ߓx�Ɏg�p����ꍇ�ɂ͓��Y�Ɩ��ɂ���ċN������̂Ƃ���C����ɂ��Ă̈ꉞ�̉𖾂��Ȃ���邱�ƂɂȂ�C�F���i��50�E2�E5���59���j�ɂ����ẮC�L�[�p���`���[�����̍�Ƒԗl�ɏ]�������J���҂ɌW�鎾�a�ɂ��ĔF��v����������Ă���B
�@���������ď㎈���r�I�ߓx�Ɏg�p����Ɩ��ł����Ă��C�����ɐg�̂̑��̕��ʂ������Ďg�p����Ɩ����ẮC��L�ʒB�L�̂P�́i3�j�ł����u�㎈�̓��I�ؘJ��i�Ⴆ�ΑŌ��Ȃǂ̂���Ԃ���Ɓj���͏㎈�̐ÓI�ؘJ��i�Ⴆ�͏�q�̑O�E��������ʂȂǂ̈��̎p�����p�����ĂƂ��Ƃ��������C������O���ʂŕێ����邱�Ƃ��K�v�Ƃ�����Ƃ��܂ނ��̂Ƃ���B�j����Ƃ���Ɩ��v�ɂ͊Y���������̂ŁC���̊�Ŕ��f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�������C�F���Ɏ�����Ă��Ȃ��Ɩ��ł��Ɩ�����r�nj�Q���͗ގ��̎��a�����ǂ��Ȃ��Ƃ͒f�肵��̂ŁC�㎈�ƕ����Đg�̂̑��̕��ʂ������Ɏg�p����Ɩ��ɏ]������J���҂��炱���̎��a�ɌW��J�А������������ꍇ�́C�F���ɂ�邱�ƂȂ��C�ʂɍ�Ƒԗl�C�Ɩ��ʓ����͈��̂����Ɩ���O�̔��f���s�����ƁB
�i2�j�O�L�ʒB�̉���W�Ɂu�K���×{�i�Ⴆ�Ζ��@�C���w�Ö@�C�̑��C��Ə�̔z���C�����w���C���_�q���ʂ��̏����E�w���Ȃǁj���s���C�����ނ˂R�������x�ł��̏Ǐ�͏��ނ���c�c�v�Ǝ�����Ă���̂́C�F�����̂��̂��y�x�̎��a�ɂ��Ă��F�肪�s����悤�ݒ肳��Ă���C�F���ɗᎦ���ꂽ�悤�ȋƖ��ɏ]���������Ƃɂ�蔭�������r�nj�Q�ɂ��ẮC�Ǐ��̏����i�K����K�ȗ×{�y�ь��N�Ǘ����s����Ȃ�Δ�r�I�Z���Ԃ̂����ɉ����Ɍ����̂��ʏ�ł���C��w�o�����エ���ނ˂R�������x�ł��̏Ǐ�͏��ނ�����̂ł���Ƃ̌����Ɋ�Â����̂ł���B
�@�������C�r�nj�Q�ɗގ��̑��̎��a�����݂��Ă��邩�K�ȗ×{�y�ь��N�Ǘ����s���Ȃ��������̏ꍇ�ɂ����ẮC�R�������ďǏ�������ꍇ������̂ŁC��L����W�͂R�������x�o�ߌ�ɏǏ��ނ��Ȃ����̂��ꗥ�ɋƖ��ɂ��Ȃ������a�Ƃ��Ď�舵���Ƃ�����|�ł͂Ȃ��B
�R�D�@�����Łi���j
|
|
|
| �S�A�����X�N�Q���u�㎈��ƂɊ�Â����a�̋Ɩ���O�̔F���ɂ��āv�i���65���j |
 |
|
�@��������59���ʒB�ɑ��A��ЎҁA�J���g�����炾���łȂ���w�E����������̖�肪�w�E����Ă��܂����B���������w�E�ɑ��ĘJ���ȁi�������J���ȁj�͂��̓s�x���̏ꂵ�̂��́u�����A���v�ȂǂŖ�������킵�F���̉�����������Ă��܂����B���65���̍ő�̖��_�́A����爫��p�̒��j��S���Ă����Γc�����������Ƃ������Ɖ�c�̂��Ƃʼn������ꂽ�F�����Ƃ������Ƃł��B59���ʒB�Ɣ䂵�ėǂ��Ȃ����̂ł͂Ȃ����ƗB�ꌾ���Ă���ΏۋƖ��̖����ł����A����ƂĂ�����59���ʒB���ł����F�߂���Ȃ��Ȃ������N��Q����ǂ��ŔF�߂��ɉ߂����A�ނ���O�q�̂悤�ɉ^���̍��܂�̒��ŁA�ꕔ�O���C����]�V�Ȃ����ꂽ�R�������ޘ_��ӕʐf�f�̋����Ƃ����������h�点�����Ƃɑ傫�Ȗ�����������܂���B�i�����A��45���́A�킴�킴�폜����܂����B�j
�@���������F���́A�S���œ����悤�ȏ����ŔF��ł���悤�ɐĈꐫ���m�ۂ��邱�Ƃɑ傫�ȖړI������܂��B�Ƃ��낪���65���ȍ~�`���q�ׂ��悤�ȕs�v�c�ȏ���o�����Ă���̂ł��B����ݏo�����65���̖��_�́A
�@�@ ����܂łƑΏێ��a�E�f�f����傫���ς���\�I�Ȃ��̂�Ꭶ���܂����B�����āA�ǂ����Ă��f�f�����Ȃ����̂��r�nj�Q�Ɛf�f����͎̂d���Ȃ����A�ł������Ǐ�Ə�Q���ʂ���肵�A����ɑΉ������f�f���ƂȂ�悤�厡��ɋ��͂����߂Ă��܂��B��Q���ʂ���肷�邱�Ƃ���Ў҂̗×{���錠�������߂Ă������Ƃ́A����܂ʼn��x��������Ă��܂����B���X�Ȏ厡��ւ̏Ɖ�A��Ў҂̗×{���錠�������߂Ă������Ƃ��̌��ς݂ł��B���Ƃ��Ə�Q���ʂ����m�łȂ��r�nj�Q�̂ق���ꡂ��ɑ����Ƃ�����w�I�W�ς�������Ƃ����܂��B
�@�A �F��v���E�]�����ԁE��Ə����ɂ��ẮA�ᔻ�̑�������59���ʒB�����̂܂ܓ��P���܂����B����ł̓O���[�v�S�������I�ɑ��������m���}�̐��s��]�V�Ȃ�����Ă��鍡���̘J�����̂��Ƃł́A�Ɩ���ƔF�肳��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�ǂ̒��x�̋Ɩ��ʂŔ��a���邩�́A�l���܂Ȉ��q�̊֗^�ɂ���Đl�ɂ�鍷���傫���o�܂��B�ʂɔ��a���̘J�������A�J�����ƌ��N�j��̊W�𖾂炩�ɂ��邱�ƂȂ��ɐ������Ɩ���O�̔��f�͏o���Ȃ����A�\�h�{��̌��ʂ������邱�Ƃ��o���܂���B�B�ꎿ�I���S���]�����邱�Ƃ��������܂������A�����A��45�����폜����܂����B
�@�B �×{���Ԃɂ��ẮA�R�����Ōy������Ɩ��m�Ɍ�����܂����B�����Ď�p�{�s�́@�ꍇ�U�����Ŏ�������B���P���Ȃ��܂܂ɒ����ɂȂ�ꍇ�A�ΐf�ɂ�萸�_��w�I�Ȍ������܂߂Đf�f�������ƁA���炩�ȗ×{���Ԑ����ɂȂ�����̂��K��ɐ݂��Ă��܂����B
�@�C �������퐶���Ƃ����ڂɊ֘A���Ă���A���̔��ǂɂ́A�Ɩ��ȊO�̗̌v���i�Ⴆ�ΔN��A�f���A�̗͓��j����퐶���v���i�Ⴆ�ΉƎ��J���A�玙�A�X�|�[�c���j���֗^���Ă���B�܂��A�㎈���ɕ��S�̂������ƂƓ��l�̓���́A���퐶���̒��ɂ��������݂���̂�����A�����̗v��������������Ŏ�舵���Ƃ��܂����B�܂�A�l�I�Ȏ�_�̂���l�B�q������ĂĂ��邾�Ƃ��A�Ǝ��J������ς��Ƃ��A�X�|�[�c���Ȃe�j�X���Ȃ���Ă���悤�Ȃ��Ƃ�����B���������l�͔F��Ώۂ���O���āA���̏�ŔF���ɍ��v���Ă��邩�ǂ����������ĔF�肷��Ƃ����̂ł��B
�@���̂悤�Ɋ��65���ʒB�̖��_�����Ďv���o�����̂��A�ߋ��E�ƕa�̍ف@�������i�F��E�ł���j�ŁA����o�c�ґ��̕⏞���ۂ̈�w�I���菊�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă����Γc�����̏،����e���A���̂܂ܕ��ׂ��Ă���̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ̎v���ł��B�������d�v�Ȃ��Ƃ́A�����Γc�����̎��_�͂��̑唼���ٔ�������ŁA��w�I�،��Ƃ��č̗p����Ȃ������Ƃ��������ł��B���̂��Ƃ́A��ɉߘJ���̔F�������ɓ������ē����̉������������������J�ДF������ɓ������č������̂�ׂ���{�p���Ɩ��炩�ɋt�s���铮�����A���̂U�T���ʒB����ɂ������Ƃ������Ƃł��B
�@���̂悤�Ɍ���ƁA�`���q�ׂ��r��Q�̘J�ДF�肪�A�ŋ߂��������Ȃ��Ă���́@���[���ł��܂��B���Ƃ���Ȃ�A����������铹�������Ɩ��炩�ɂȂ��Ă��܂��B
|
|
|
| �J�ДF�蓬���̔��W�Ƌ��P |
 |
�P�A�F�蓬���̊�{�́A�{�l�������̐g�̋�̈����Ǝd���̊W���A���������Ă���́@�o�߂�ǂ��ď[���F�����邱�Ƃɂ���܂��B���̂��߂ɊȒP�ȃ����ł��ǂ�����A�d���̓��e�����߂Đڂ���l�ł������ł���悤�ɏo���邾���ׂ��������o���B�����āA�ǂ�Ȏ��ɂǂ�ȕ��ɐg�̋�������Ȃ��Ă��������d�����e�ƑΔ䂵�Ȃ���ꗗ�\�ɏo����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�ܘ_�����Ɏd����̃A�N�V�f���g�����l�̑����Ƃ��d����̓˔��I�o�����ȂǗL��Δ��l��������ă������Ă����Ƃ�藝�����i�ނł��傤�B���̒������ōl����̂ł͂Ȃ��A�����o���ĊO���猩�Ă����i�q�ϓI�j�K����t���邱�Ƃ���ł��B
�Q�A�����ŁA���̐l�Ɠ��l�̐g�̋�̈����Ȃ肩���������E��̒��ԁA�����d�������Ă��钇�ԁA�����悤�Ȏd�������Ă��钇�Ԃɂ���������̂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��ā@�������ƂɂȂ�܂��B
�R�A�����āA����������𗝉����āA���̕a�C�̋Ɩ��N�������͂�����Ə��F�����t�̎x�����邱�Ƃł��B�Ԉ���Ă��̎���C�̂����ɂ����t�Ɋ|����ׂ��ł͂���@�܂���B����Ȉ�t�Ɋ|�������炩�����ĕa�C�͈������A��ɘJ�А\�����s�����ہA�Ɓ@���O�̌�����^���邱�ƂɂȂ�܂��B��Ȉ�t��I�Ԋ�͎��̂悤�ɍl�����܂��B�@�`�A�J���҂�J���g���ɕΌ����������A���a�ƘJ���̊W�ɂ��ė����������A�܂��͗������悤�Ɠw�߂��t�i��������ɏo�����A�J���҂̐��̑i���J�ɕ����Ă�����t�j |
|
|
A�A |
�J���҂�J���g���ɕΌ����������A���a�ƘJ���̊W�ɂ��ė����������A�܂��͗��������悤�Ɠw�߂��t�i��������ɏo�����A�J���҂̐��̑i���J�ɕ����Ă�����t�j |
|
 |
�a�A |
�E�ƕa�̎��Âɂ�����A�����̊��҂ɐM������Ď��сA���ʂ������Ă����t�i���҂����܂₩���̂ł͂Ȃ��A�a�C�Ƃ̓������܂���t�j |
|
 |
�b�A |
�Ǐ�Ǝ��Õ��@�ɂ��āA���m�ŋ�̓I�Ȑ�����[���̂����[�u���Ƃ��Ă�����t�i�J�Еی���E�ƕa��ɂ��ė����̂����t�j |
|
 |
�c�A |
���{�Y�Ɖq���w��̓��ꌩ��ϋɓI�Ɏ��ꌤ���I�ӗ~���������H���Ă�����t�i�������A���҂��������b�g�����ɂ��Ȃ��j |
|
 |
�@���A�J�А\�����������A�J�����J�Еa�@�ȂǂɎ�f���߂��o�����ꍇ������܁@�����A���̎�f�͋C�����Ȃ�������܂���B���̂���܂ł̑̌����炢���āA�Ɩ��O�̌����Ɏg����댯������������ł��B����Ȏ��͒P�Ɂu�s�������Ȃ��B�v�ƁA�f��̂ł͂Ȃ��A���̎�f�̐��i��������Ɛ����A��f���߂��鎞�A�J������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������s������Ă��邩�m�F���邱�Ƃ���ł��B�悸�ӕʐf�f�̖ړI�͉����B�厡��ւ̏Ɖ�ŕs�\���Ȃ̂͂ǂ����B���̂킯�́B��f��̈�t���ӕʐf�f�ɑ���������t�Ȃ̂��A���̈�t�̂���܂ł̋Ɛт́B��Ў҂ւ̑Ή��Ŗ����N�����Ă��Ȃ����E�E�E�Ȃǂł��B�����āA�����^��ȓ_����������Ȃ��Ȃ������Ǝ�f�ł��Ȃ����R���q�ׂāA��f���߂ɂ������đ�U�R����ł̕��ь��c�̗��s�����߂Ă������Ƃ���ł��B
�S�A��Ɠ��ŕ⏞����ꂽ��F�蓬���͕s�v�Ƃ���X��������܂����A����͓����҂̐��@���ƌ��N�������g�݂ɂƂ��Đ������Ƃ͌����܂���B��Ɠ��ŕ⏞���邩������@�O�֏o���ȂƂ���������́A�����J�b�g�Ȃ��Ɏ��ԓ��ʉ@��F�߂����w���Ɋ|���@���Ă���A�w���̐f�f�������F�߂Ȃ��Ƃ���������Ɠ����悤�ɁA���ǂ͘J���ҊK���̂��߂ɂ���a�҂̂��߂ɂ��Ȃ�܂���B�܂��A�F�肪��ꂽ���Ƃɕ⏞�����悤�B�S�Ă͔F��҂��Ƃ����̂��������Ƃ͂����܂���B
�@�J�ДF��̎��g�݂͂��ꂾ�����藣����Ă�����̂ł͂���܂���B�w�F��E��@���\���Á\�\�h�\�E�ꕜ�A�E�Ĕ��h�~�x���A�ƂȂ��Ă��݂����ڂɊ֘A�����������g�݂Ƃ��Đi�߂Ă����˂Ȃ�Ȃ����̂ł��B���̎����̂��߂Ɋ��p����̂��J���s����g�ݍ��܂���Ƃ������Ƃł��B�J���ȁi�������J���ȁj���u�J�А\�������ꂽ��A�J�Е⏞�ۂ������Ή�����悢�ƍl����̂ł͂Ȃ��A���Ăɂ���Ă͊ēƈ��S�q���ۂ��O�ʈ�̂ƂȂ��ĘJ���s���Ƃ��ĐӔC���ʂ����悤�Ɂv�ƁA�Ɩ��w�j���߂Ă��܂��B
�T�A�������ԑS�̂̐����ƌ��N����铬���̈�Ƃ��āA�܂��E�ꂩ��J���g�����������@�J���^�����������Ă��������̈�Ƃ��ĔF�蓬���𗝉����ʒu�Â��邱�Ƃ��厖�ŁA�@���ʂɋC�̓łɂȂ������킢�����Ȍl���~�����߂̓������Ƃ������ɂȂ��Ă͂����܁@����B�F�肪���Ȃ��Ă��u�������v�A�J���������������ǂ��A�J�����������P�ł���Α傫�ȏ����Ƃ����܂��B�t�ɔF��͎��Ă��u�������v�J�������͉v�X�i�߂��A�g�����キ�Ȃ�悤�ł͏����Ƃ͂����܂���B
�U�A��a�҂ɂƂ��Ă͔F�肪���Ȃ��ł����܂���������A�F�肪���Ă����܂ł����@��Ȃ���肸���Ƃ܂��ł��B��a�҂����܂����邽�߂̈�Ƃ��ĔF�蓬���Ɏ��g�ށ@���Ƃ��厖�ł��B���̐E��ɖ߂�Ȃ��悤�ȂƂ���܂ň����Ȃ��ĔF�肳���̂́A�F�肳��Ȃ����͂܂��ł����A�{���ɂ������Ƃł͂���܂���B�Z���Ԃ̋x�ƂőS�����Č��̐E��œ�����A�S�R�x�܂���̘J�������̌y���Ɠ����Ȃ��玡�ÂőS�����Ă��܂��Ƃ����i�K�ŔF������Ƃ����̂��]�܂����Ƃ����܂��B
�E�ƕa�����̒��ŁA�F�蓬���͌����Ƃ��āA�o���_�łȂ���ΏI�_�ł�����܂���B��a�҂����܂�����A�܂�������悤�ɂȂ邽�߂̑S�ʓI�ȓ����̈�ł���A�J�����������P���ĐV������a�҂̑��o��h�����߂̑S�ʓI�ȓ����̈�ł���A�J���҂̒c���ƘJ���g���E�J���^���̋����E���W��E��ŁA��Ɠ��ŁA�Y�Ɠ��ŁA�n��ŁA�����đS���I�ɑ��i����S�ʓI�ȓ����̈�ł���Ƃ����ʒu�Â����厖�Ȃ̂ł��B���̓_�ł́A�u�r��Q�v�𑽔������Ă�����v�ȐE����A�ۂ��Ɖ�������������p�[�g�J���ɓ]�����鎑�{�̉��\�������A���ʓI���r��Q�Ƃ����[���Ȍ��N��Q����݉������Ă��܂������Ƃ́A�傫�Ȕ��ȓ_�Ƃ��Ȃ�������܂���B
|
|
|
| �F���̐������Ƃ炦�� |
 |
�P�A |
�@�F���̖ړI�́A�s�K�v�Ȓ����Ɏ��Ԃ��������A�E�ƕa���N������v�ȏ����A�a�C�̌�����ɂ��F��̍l�������������Ƃɂ���āA���₩�Ɍ�����s�����Ƃɂ���܂��B
�@�J�Еی��@�̖ړI�́A��Ў҂̌����A�v���ȋ~�ςł��B�r��Q�̔F��ł́A���Ȉӌ������܂ߐ����������\�������Ă���ꍇ�ł��\�����ĂR��������V�����|�����Ă��@�܂��B���̎��g�݂��ォ������J��ւ̒Nj�������Ă��Ȃ��ƂP�N�Ƃ��Q�N�|�����@�Ă��܂��܂��B�����ی�@�ɂ��u��Õی�v�͐\�����Ă����T�Ԉȓ��Ō��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����K��ɔ�ׂđ傫�Ȗ��ł��B
�@�܂��A�s���̑����Ɩ��͓c���p�h��������b�ł��������A�\������P�����ȓ��ɏ����@�ł��Ȃ����́A�\���҂ɂ��̗��R���������悤��߂Ă��܂��B�����S���J�АE�ƕa����s�ψ���̎����ǎ��������Ă����Ƃ��́A�x�X���̋K����g���Ĕ�Ў҂̑����~�ςɖ𗧂ĂĂ��܂����B���̋K��͌��݂������Ă��܂��B�ϋɓI���p�����肢�������Ǝv���܂��B |
|
 |
�Q�A |
�@�F���ɊY�����Ȃ�����Ƃ����āA���Ɩ��O�Ƃ��ď������Ă������Ƃɂ͂Ȃ��Ă��@�܂���B�F�����ӂ邢�킯�Ɏg���Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B�Y�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̌o�߁A�Ɩ��̎��ԁA���a����Ɏ������E��̏������𐳊m�ɑ����A�Ɩ��ƕa�C�̈��ʊW���m�F������Ō��肵�Ȃ�������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B�J���ȁi�������J���ȁj�̔F���Ƃ̋Ɩ�������ł́A�F���ɊY�����Ȃ��ꍇ�ɂ͔��_�̋@���^���˂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B |
|
 |
�R�A |
�@��w�I�ȔF���̔��W��₦��������A�F�莖��̏W�ςɂ��s���o�������邱�@�Ƃɂ���āA�F������荇���I�ʼn~���ȕ⏞�[�u���s������̂ɂ��Ă������Ƃ����@���ɂ͋`���Â����Ă��܂��B���̓K���Ȏ�����v�����邽�߂ɔ����Ēʂ�Ȃ��̂���@�w�I�R���Z���T�X�̓����ɂȂ�܂��B�����ĎY�Ɖq���w��ɘJ���ҁE��Ў҂̐��̐��ڔ��f������@�������Ă��܂������A�����ł͂����������g�݂��キ�Ȃ��Ă���͔̂ۂ߂Ȃ������ł��B�܂��A�J���҂̐����ƌ��N����铬���̏����̒i�K�ł́A��Ў҂̌@��N�����Ƌ~�ρi�f�f�E���Áj�A�w�p�I�����E�𗬂�ʂ��Ă̖���N�ȂǂŐ��I�������ʂ����Ă�������A����p�҂��炽���A����f�Â���܂܂Ȃ�Ȃ���ɂȂ��Ă��܂��B�l�X�ȗv�������G�ɗ��ݍ����č����̏�����o���Ă����̂Œ����ɉ����Ɍ��т�����͂���܂��A������x���_�ɖ߂��āA���ڂ̑O�ɂ�����̔�Ў҂̘J�ДF��l���̐ςݏd�˂��d�v�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B |
|
|
|
* ���S���J�АE�ƕa����s�ψ�����ǎ���
�@�i�E�Ɛ������E�u�w���T�[�`�Z���^�[�Ď��j |
|
|
�i�Љ�J���q���@vol.5-2�@2008�N��T����Q���@�m�o�n�@�l�E�Ɛ������E�u�w���T�[�`�Z���^�[�j
|
|
|