|
特集
|
職業性疾患・疫学リサーチセンター
|
|
設立記念講演
|
|
職業病から学んだ慢性疲労・慢性疼痛の診かた
| 渡辺 靖之 |
| 職業性疾患・疫学リサーチセンター 副理事長 |
| 芝大門クリニック 所長 |
はじめに
私は昭和43年に北海道大学医学部を卒業し、大学病院整形外科で研修しました。そこでは主に脊椎外科の先輩について助手の記載係で勉強していたのですが、その当時に、整形外科の病気ではないのですが首、肩、腕のこりの痛みの患者さん、若い女性の患者さんで、銀行員のキーパンチャーの方がたくさんおりました。中には非常に重症な方がおられて、これは病気なんだろうか、どんな病気なのだろうかということに興味を持ちはじめて、とうとう現在に至るまで頸肩腕症候群の臨床の仕事をやってきました。
当時の日本は、おそらく世界の歴史の中でもまれな高度経済成長期で、たとえば銀行員の方も、それまでは銀行に入ったらば1年目はこういう仕事、2年目はこういう仕事というふうに、だんだんと仕事を覚えて熟練して行くのですが、このころは銀行に入ったらすぐキーパンチャー室に集められてキーパンチャー業務をさせられたというふうなかなり特異な時代でした。
その少し前に、電話機・電話交換が非常に発達しまして、電話交換手さん。キーパンチャーの仕事に少し遅れてダイエーとか灘生協、大型のスーパーマーケットのレジ係り。当時のレジは手で打鍵入力していました。片手で荷物を取りながら打鍵する。そのような職種の人の間から、まずは腕、手の痛み、腱鞘炎ということで始まったのですが、手指や腕の痛みだけではなくて首や肩のこり、痛みがひどくなり仕事を続けるのが困難になるという罹病者が非常な多数にのぼりました。
やはりまず東京から始まり、大阪、名古屋という大都市から、小都市にも急速に波及していきました。私がいましたのは札幌。札幌にはやや遅れて波及してきました。札幌から、更に例えば釧路とか網走とか小都市に波及していきました。ということで東京、大阪、名古屋で、当時重症の患者さんたちを診ておられたドクターたちはだいたい私より5、6歳年上の方々で、今ではほとんど頸肩腕症候群の臨床から引退されています。私は少し遅れてこの道に入りましたので、今年ちょうど年男で還暦ですが、まだ定年前で臨床の現場に残っております。
頸肩腕症候群は「単なる肩こり、目の疲れ」ではなかった
頸肩腕症候群というのは、今でも「単なる肩こり、目のつかれ」というふうに思われている方も多いかと思いますが、頸肩腕症候群の中には非常に重症な方がいまして、こういうふうに言っても信じられないかもしれませんけれども、2、3年休業しても、それでも日常生活さえ不自由、就労はまだまだ先という方がかなりおられます。また中には5年10年と休業、療養しても職場復帰できない方もおられます。
頸肩腕症候群はもちろん一夜にして重くなるわけではなくて、こりやだるさは我慢して、痛みやしびれをだましだまし、病院にも通い治療院にも通い、なんとか働きつづけてだんだん重くなるものです。
日本では海外に先駆けて昭和40年代後半にはすでに、腱鞘炎とか頸肩腕症候群という病名がつけられ、職業病であろうということになり、患者さんとして、はじめに病院にかかる窓口は整形外科でした。しかし、教科書的にはっきりした他覚的所見が乏しく、また手術の対象にならない病気であり、窓口であった整形外科では馴染めない病気と考えられて、一部の精神科の先生方がつけた半分ノイローゼ、真のノイローゼとは少し違うということで「半ノイローゼ」。それから、職場に対応できない、今で言えば不登校のような病気ではないかということで「職場不適応」という考え方が広まったりもしました。
当時の整形外科、脊椎外科の中では一番のスターだった某有名医大の某助教授が次のように発言しました。「頸肩腕症候群というのは頚椎椎間板症(椎間板軟骨の変性、障害)の前触れ。そのうちに、半年か1年後には頚椎椎間板症になる。騒ぐほどの病気ではない」ということで片付けられそうになった時期もありました。
しかし先ほども言いましたように、休業休養しているにもかかわらず、何カ月、何年という長期間にわたって社会復帰できない非常に重症難治化した患者さんが、この時期には非常に多かったわけです。世界中でもこれほど多くの患者さんを経験した国はおそらくなかったと思います。
中村の病型分類
そのときに患者さんがたくさん集まってきて、その非常に多くの患者さんを丁寧に診ておられたのが東京民医連の内科医で、芝病院の先輩で、すでに引退された先生ですけれども中村美治がおられまして、頸肩腕症候群の重症難治となった人のタイプをこのように五つに分けました。
最も重症な――上から順番に重症と見ていいのですが――反射性交感神経症タイプ。半身縦割り型に感覚が「鈍い」のですけれども、その側が非常につらい。半身を切り取ってほしいというようなことをおっしゃっるような症状所見を持った患者さんがいました。
次に半身感覚障害はないが、全身すべての筋肉にこりが拡がって、長期の休養や治療でもこりが取れないというふうな広範筋硬症というタイプ。
3番目には、重なる点もあるのですけれども、握力や背筋力が非常に低下して、その回復が著しく悪い、全身の脱力を主としたタイプ。
4番目には書記作業者の手指痙攣(けいれん)、書痙(しょけい)と言うのですが、字を書こうとすると、手がこわばったり変に動いて字が跳ねたりして字が書けなくなる。右で書けないものですから左で字を書く練習をするけれども、今度は比較的早く左でもまた書けなくなってしまう、これは大昔から知られている書痙のタイプ。
5番目には、ともかく異常に強い疲れやすさ、倦怠感のタイプ。
この5つのタイプに分けられました。
私は当時整形外科にいて、従来知られている整形外科や内科の病気に「当てはめよう、当てはめよう」と考えていたのですが、それでは頸肩腕症候群、胸郭出口症候群、腱鞘炎などという整形外科的な病名診断は出来るのですが、それ以上の「深い」診断とはならずに悩んでいました。
そうした時期に中村先生の論文を読みまして、霧がどんどん晴れて行くように分かって行くというような気持ちになったことを、今だにありありと覚えています。中村分類を使ってみると、重症難治化した患者さんの病態がよりよく理解できるようになったわけです。
当時の東京は重症難治の頸肩腕症候群の宝庫みたいなもので、中村先生は多数の患者を専門的に診療した結果、臨床特徴を総括して以上の5つの病型に整理されました。
この5つの病型にはまっていればいるほど重症難治化しているわけです。また途中経過や回復具合は、この病型が薄れてくることで分かりますし、握力・背筋力の計測値が経過を見るのに今でも最も重要で必要不可欠な方法です。
頸肩腕症候群の診察室での身体所見
われわれ臨床医というは、病院のほうにいて、しかも診察室にいて患者さんが入ってくるのを待ちまして、患者さんの体を診察して自覚症状に見合った所見を見つける。それから検査で検査所見を見つけるというのが仕事です。
自覚症状やそのための障害の経過がいくら深刻であっても、他覚的所見や検査所見などの裏付けを取ることが出来ないと、自信をもって立派な病気です、と患者さんにも言うことができないし、診断書を書くことが出来ないのです。また重症度を判断することも出来ないわけです。
頸肩腕症候群の場合には職業病ですから、職場の上司が来たり労働組合の方が来たり家族が来たり、労災申請すると労働基準監督署からいろいろ聞かれて、本当に病気なのか、見通しはどうなのかということを聞かれますので、この点について非常に苦労したわけです。
私自身のその後の進路なのですが、整形外科というと、頸肩腕症候群の診療は片手間にやらざるをえませんし、もっとちゃんとした整形外科医になろうと思うと、整形外科の勉強をしなくてはなりませんし、手術も上手にならなくてはならない。整形外科医は、午後から手術に入ると、手術が終わったあと夕方には疲れ切ってしまい、なかなか勉強するというわけにいきませんので、忙しい整形外科をやっていたのではだめだということで、当時少しはやりかけてきた心療内科に替わろうかと思いました。しかしいろいろ調べまして、やはり身体の所見をきちんと把握するためには神経内科のほうがいいのではないかと考え、そちらを選びました。心療内科というのは精神科のようなもので、神経内科というのは脳外科の外科をやらない科目です。
当時北海道には、神経内科教室がなく、脳神経外科の中に神経内科診療班がありましたので、そこに入れてもらって神経内科の勉強をしました。
頸肩腕症候群に、何か検査で客観的につかめるのではないかと考えて、脳波や誘発電位や筋電図なども勉強しました。またその延長線で脳波の勉強を仕上げたかったものですから、思い切って、静岡に「てんかんセンター」がありまして、そこの先輩を頼って本州に出て参りました。
てんかんセンター、静岡東病院はてんかん病の専門病院、研究所です。てんかん、脳波では日本で一番やっていますので、脳波の勉強になるのではないかなと思いまして、2年間勤務し、勉強させてもらいました。しかし結果的には、脳波というのはてんかんの診断道具ではあるけれども、頸肩腕症候群とは何の関係も無いということがますますはっきりしました。
やはり患者さんをたくさん診ることしかないなということを決心して、東京民医連の職業病センターとなっている港勤医協芝病院で働かせてもらうことにしました。
芝病院では、すぐ自分の頸肩腕症候群外来も開いたのですが、そうたくさんの患者さんがいるわけでもないし、当時海老原先生が一人でじん肺の臨床をがんばっておられましたので、僕は病棟係で、じん肺診療のお手伝いも経験させていただきました。
当時は胃潰瘍治療薬シメチジンもまだ一般使用されていなくて、じん肺患者さんが、呼吸不全で苦しみ、その結果胃潰瘍になって吐血して亡くなる方も多かったことを思い出します。
それから、当時は芝病院には産業中毒、鉛中毒や慢性有機溶剤中毒の患者さんもたくさんおられまして、その患者さんも担当しました。
そうした職業病で苦しんで自殺された方、自殺を図られた患者さんも多くて未遂の方もおられましたが、亡くなられた既遂の患者さんは、私が芝病院に来て最初の7年間にちょうど7人もおられて、非常にたいへんな病気だということをつくづく思いました。
さて本題の頸肩腕症候群のことですが、私はできるだけたくさんの過労性疾患の患者さんを診ようと思って、東京の芝病院に参りました。
芝病院に来て多くの患者さんを診療して、やはりいろいろなことを考えさせられました。
やはりいの一番が自覚症状。仕事や日常生活の不自由度というのが、もちろん基本と思いました。ただし、これもただ漫然と問診すれば良いのではなく、システム化しなくてはなりません。芝病院の過労性疾患診療では長らく産業衛生学会頸肩腕障害問診表を用いて来ました。また日常生活障害度では「慢性疲労症候群」の症度表を用いています。
診察所見としては、身体を触ってこりと言っても、マッサージの先生たちの多くはこりがわかると言うのですけれども、私は何回も治療院に見学に行ったり、時間をかけて患者さんの身体中触るのですけれども、こりの程度がどうしても分からない。筋肉が発達しているのかこっているのか分からない。もちろん、ある程度のこと、いわゆる肩こりの部分などは分かるのですけれども、全身にわたってはどうも分かりづらい。
それから圧痛点というのが昔からある言葉なのですが、圧痛というのは強く押せばそれなりに痛いですから検査者によって非常に違いますし、良く分からない面があります。患者さんの身体をいくら触っても、この辺にこりがあると言えばあるし、ないと言えばない。圧痛点があると言えばあるし、ないと言えばない。そうするとカルテにはきちんと書くことができないわけです。これでは他覚的所見ということにはなりません。
眼精疲労ということもなかなかつかめない症状です。眼科受診して検査を受けても、せいぜい近視と言われるぐらい。眼科の治療に乗らない。眼科的にも頸肩腕症候群の重症度度を測ることは出来ない。
画像診断、レントゲン検査、CT検査、その後MR検査が普及してきましたが、これらの画像検査は、頚椎症などほかの病気を見つけるのには非常に重要な、といってもあくまでも補助ですけれども、頸肩腕症候群にとっての他覚的所見ではないのです。
握力と背筋力、あとピンチ力など筋力測定値ということがありますが、これは学校の体力測定でも使いますし、健康測定にも良く使われます。
握力や背筋力値が非常に落ちるということは、頸肩腕症候群が重くなればなるほど低下することはもちろんよく分かりますし、私自身も札幌時代から当然診療の中に用いていました。しかし握力、背筋力というのは患者さん自身が自分で測るものですから、重く見てもらいたい人は力を出さなければ出さないで済むわけです。それから測るときに、数字が良く出ても針を戻すとか、出てもきちんと書かないで低い値を書くことも可能です。そういう点で他覚的所見としては頼りない面が確かにあります。また計測すると、かえって腰痛が悪くなるので適当に測るということがあるのではないか、ほとんどの臨床医がまずはそう考えると思うのですが、私もやはりそういう考え方からなかなか抜け出せなくて、測ってはいましたけれどもそれほど重視しなかったのです。しかし、芝病院で中村先生と一緒に仕事をさせてもらって、一番目にこの問題に直面して考えて、次のように考えに至ることが出来るようになりました。
握力・背筋力の測定値の意義
握力や背筋力は毎回簡単に計測することが出来きる計測値です。計測値の変動にはいろいろな要素があると思われますが、それはどんな計測値、血圧測定値の変動だって同じことですが、患者さんの経過を見ていくと非常によく症状経過に相関します。
芝病院では、最初の計測だけは指導して行いますが、あとは患者さんが自分で計測して記入します。これをいいかげんにやる患者さんはほとんどいないのではないかと思います。 毎回ほとんど同じ数字という患者さんは今まで20数年間で2、3人だけです。しかし逆にそういう患者さんにはまたそれなりの問題があるかなと気づかされるわけですし、その記録にもなります。
中村先生は握力・背筋力計測を非常に重視しておられて、毎回測ったものを手書きでグラフ用紙にきれいなグラフを作っておられました。グラフにすると、症状経過と良く相関することが、それこそ目にみえて分かるわけです。
握力計はおそらく1、2万円。背筋力計も2万円ぐらいのものなのですが、たった4万円か5万円の道具で測れるもので、たいていの整形外科医から意味が無い検査と思われているものなのですけれども、これがやはり非常に大事なのだ、高血圧の診療にあの血圧計がかかせないのと同じぐらい大事なことだと考えることが出来ました。
握力・背筋力の計測値の重要性を受け入れるかどうか、この問題は私にとっても非常に重要なポイントでした。
握力・背筋力の計測値グラフの実際
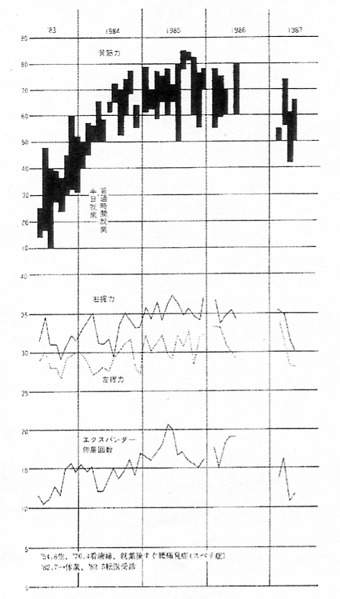
武田紀子さんが中村式にまとめた計測値グラフです。棒グラフの一つが背筋力1ヵ月の最大最小で、全体で一年間の背筋力の経過です。見えづらいですけれどもここが80〜70kg。このへんが40kgです。背筋力40〜30ぐらいで休業療養した人が、休業してだんだん良くなって背筋力80kgぐらいに回復して就労する。その後また少し落ちるという、そういうグラフです。
線グラフが握力値の経過。握力は女性の正常値が右左とも大体25kgです。
握力は1ヵ月の平均値をポイントにしてグラフに入れるのですけれども、握力の場合も症状経過と同じ相関をするのですが、背筋力に比べると幅が少ないので分かりづらい。エキスパンダー伸展回数もグラフにいれます。
私は、日常診療ではこのようなにきれいなグラフを書かずに、めんどうくさがりやなものですから、だいたい数字だけを頭の中で追っていくだけです。本当はこういうふうにグラフを作るといいのですが、症状経過と計測値が本当によく相関します。このグラフを患者さんにも見せると自分の病状の実際の経過が良く理解できるし、療養の励みにもなるわけです。
まめな患者さんは自分で経過表を作ったり、中村先生のようにグラフにしている方もおられます。ほんとうに高血圧の人に血圧を測るようなものだというくらい大事な検査なのです。
こり、圧痛は計れるか?
頸肩腕症候群の診察室の診察所見としての「こり」というものは、客観的に見れるのかどうかというのがずっと問題でした。この点に関してかなり前から筋硬度計というのがありまして、各社が開発して実際すでにスポーツ医学とか産業医学には導入されています。
30万とか40万円くらいで、高いのでまだ買って使ったことはありません。実際に頸肩腕症候群への診療や健診への導入はおそらくたいへん難しいと思います。なぜなら、握力・背筋力測定値と違って統一的な標準値を設定しがたいとか、また例えば一定の姿勢で一定の部位、肩こりの部分を測定しても、その部分の測定値だけでは、頸肩腕症候群全体の重症度を推し量るのは無理だから、とか全身的に計ることが時間的にも技術的にも無理だろうなと考えられるからです。
しかし使い方によってはいろいろ意義がある可能性も考えられますので、今はぜひ買って試用してみたいと考えているところです。
さて、私たちの過労性疾患グループでは、「こり」というものは本当に客観的に評価できるものかということを検討してみました。
それは1998年のことでわりと最近なのですけれども、マッサージ師の方4名(黒岩、小日向、菅井、熊谷)それに武田さんと私、過労性疾患チームで検討いたしました。何人かの患者さんをマッサージ師の4人の方に、全身のこりを判定してもらいその判定結果を比較して検討するということを行いました。
こりの程度に点数を付けまして、ぜんぜんこっていないものを0で、非常に強くこっているのを4点というふうにしまして、その間は1、2、3点で、5段階。ひとりの患者さんを、4人のマッサージ師の先生に触診してもらいまして、頭の下から手足まで全身のこりを評価してもらいました。
その判定結果を検討してみますと、客観的という点では、まちまちだということが分かったのです。
結果の特徴を言えば、例えば普段に黒岩さんが担当している患者さんについては、黒岩さんでは評価がこるというほうに傾くのですが、自分が普段担当していない患者さんについては、あまりこっていないというふうに傾くという傾向がありました。
というわけで、全身のこりの客観的評価というのは非常に難しいというのがこれでわかりました。「こり」というのは、マッサージ師の先生たちに時間をかけて評価してもらっても、客観的に評価するのは無理。診察室で医師が評価してカルテに記載するのは無理なことと、それははっきりと諦めることにしました。
「こりの拡がり」―こりの相対的評価法の開発―
それで今度は、「こりの拡がり」を調べるということに考えを変えました。「こりの拡がり」という概念ですね。
肩こりの部分、ここは誰でもまっさきにこりを自覚する場所ですね。
この部のこりの左右差を聞きながら触診して、弱い方を10点ということにしまして、こりの強い方を10何点かに自己判定してもらう。
例えば、図2−1の方の場合は項部が左右とも10点にすると、脇が10点、鎖骨の下は11点、腕は10点、腰は8点で、ふくらはぎは6点というふうに。
そういうふうにしまして、マッサージの専門家ではない運動療法の武田さんや若いドクターにも同じように検査者になってもらいました。
この検査結果は、ベテランの医師である私も含めて三人の検査者の結果はよく相関しました。この方法のほうが良いという結論になって、それ以来この診察法を標準化して診療に導入いたいました。
これでカルテに「こりの拡がり」を記載できるわけです。
またこうして、今まで診察室ではそれほどきちんとは患者さんの全身には触診が及んでいなかったのを、一応くまなく触るようになりました。それも目的意識的にです。しかも診察法を標準化できれば、これはそれほどの時間はかからないのです。いそげば2、3分でなんとかできるくらいです。
こういうふうにして全身を触診するようになりましたら、先ほどの「反射性交感神経症」の場合、半身がしびれている、鈍感だけれどもつらいという方では、半身感覚障害の側は調べづらいのです。それで感覚障害のない側だけ点数を付けることにしました(図2−2)。

「こりの拡がり」検査にもまた問題発生
反射性交感神経症、半身感覚障害の場合には、あまり苦労せずに診察法上の問題点が解決できたのですけれど、患者さんの中には、まだ「こりの拡がり」の検査法が上手くできない人がいることにぶつかりました。
診察の度に点数がつけづらい、痛いといって逃げたり、15点と言ったり20点と言ったりで判定しづらい。どうして何回やっても分からないのだろうというような患者さんが何人もいまして、何かいつも検査がきちんとできないという方がいまして、困っていたのです。診察するこちら側も、診察されている患者さん側にも欲求不満が残る。
そういう時期に、私は元整形外科医だったものですから腰痛症も担当もしていますけれども、ある時入院患者さんで腰痛症で、それも腰椎椎間板症の患者さんが二人おられました。
一側の腰殿部が痛いというのは腰椎椎間板症ではほとんど当然のことなのです。そこが痛いというのは当然で、普通はそこを深押しをすると痛い。そういう圧痛点があることは珍しくないというか普通です。
しかしこの時の二人の腰椎椎間板症の患者のうちの一人のかたは、障害児学級の先生をされていた方で仕事中にギックリ腰を起こして、腰椎椎間板症という診断で入院安静加療中でしたが、急性期の痛みは退いて、慢性期に入っているはずなのに何でこんなに痛がるのか訝しいと感じ始めていました。この部位を少し触るだけでも痛いというのです。病室回診の際に軽い触診でさえも身体が自然に逃げてしまう。
またもう一人の方が、たまたま隣のベッドにも、もう一人同じ腰椎椎間板症で入院安静中の、職業は保母さんの方がおられましたが、この方もたまたま同じ側に、前の方ほどひどくはないのですが、やはり軽い触診でも身体が逃げるように痛がる方がおられました。
今までの腰椎椎間板症の痛みとは、どうも少し様子も経過も違うな、不思議だなと思っていました。
この事について、だんだんとはっきりと意識的に気付きまして、「問題であると明確化する」ことが出来ました。
「過敏性腰痛症」の発見
圧痛といえば圧痛ではあるけれども、普通の圧痛点ではない。
それで指の頭で軽く叩く、叩打というのですけれども、指の頭で叩くという診察をしましたら、この痛みの場所はかなりクッキリと境界が鮮明であることが分かりました。この範囲内では、押す、叩くなどの刺激に対しては非常に過敏です。患者さんの身体の他の部位にはそういう場所はありません。
慢性の腰痛症の中には、こういうケースが他にもいるのかも知れないと思いまして、外来で担当していた腰痛症の患者さんを同じ診察法、叩打法でどんどん調べてみました。
そうしますと、痛がりかたの程度は軽重さまざまですが、叩打痛圧痛の範囲がハッキリしていて記載できるようなケースは結構多くて、慢性の腰痛症(ほとんどは腰椎椎間板症でした)では10パーセントくらいの割合で見つかることが分かりました。しかもそれらの患者さんはほとんど全部と言ってもいいほど腰痛症としては重症難治化していることが分かりました。
カルテの記載例を示します。経験した中では、先ほどの二人の入院患者さんの場合には図のように叩打痛圧痛領域が見られました(図3−1、図3−2)。
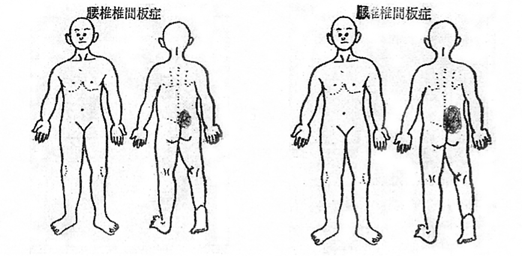
また同じ腰椎椎間板症の場合でも、通常の椎間板性疼痛の範囲をはるかに超えて、両側の背中から大腿部まで叩打痛圧痛領域が拡がっているケースも見られました(図4−3)。この方の場合はその後も5、6年間ぐらい今も休業療養中です。しかし幸い今では叩打痛圧痛領域はかなり縮小してきており、日常生活活動度もかなり改善して来ています。
また通常の腰椎椎間板症では、痛みなどのために運動制限は前屈のほうに強い制限があるのが普通ですけれども、叩打痛圧痛領域を有する患者さんの場合の特徴として後屈の方が痛みのためにほとんどできない。
また背筋力が非常に低くて、なかなか改善してこない。そして何よりも叩打痛を認めるケースは、非常に難治化だということです。
腰痛症中でも多くは腰椎椎間板症ですが、その中に叩打痛圧痛領域が認められ、腰椎後屈制限が著明で疼痛があり、背筋力低下も著明、非常に難治化している、これらのセットで考えることが出来る一群を、とりあえず「過敏性腰痛症」と名前を付けました。
こうした病態はもちろん昔からあったに違いありませんので、昔私が整形外科の研修医だったころにはすでにもう死語となっていた「脊椎過敏症」、もしかしたらそれがこの「過敏性腰痛症」ではないだろうかと考えています。
頚椎椎間板症にも叩打痛圧痛領域
さて、叩打痛ということに着眼して診察してみると、同じ椎間板症ですが頚椎椎間板症のほうなのですけれども、やはり図のケースのように、頚椎の場合にもやはり同じように叩打痛・圧痛があるケースが見つかりました(図4−1)。
それからまた、上腕骨の内、外側上顆炎、手を使う仕事、腕を使う仕事、スポーツで肘が痛くなる病気なのですが、やはり普通の圧痛点を超えて、腕全体、しかも指先にまで叩打痛が認められる患者さんがいました(図4−2)。
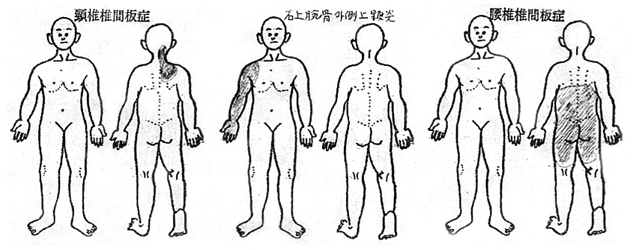
|
図 4-1
|
|
|
図 4-2
|
|
|
図 4-3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
図 4 叩打痛圧痛領域
|
|
|
|
頸肩腕症候群にも叩打痛圧痛領域
さていよいよ頸肩腕症候群ですが、頸肩腕症候群でもやはり叩打痛を認める患者さんが少なくない、かなり多い、ということが分かって来ました。
先ほどの「こりの拡がり」が調べづらいという話につながるのですが、叩打痛領域があるために「こりの拡がり」を調べづらいということが分ったのです。それで頸肩腕症候群でも、まず叩打痛を調べるほうが効率がよいのです。
頸肩腕症候群の場合には筋・筋膜のこりが元々の始まりですから、結果的に今から考えると叩打痛を認めることが多いのは当たり前だったのです。叩打痛は「こりの拡がり」の上に叩打痛が乗っかって現われるようだと分かってきましたがその現われ方、叩打痛の領域の拡がり方、は非常に多彩ではありますが、ある程度の法則もあるようです。
例えば頸肩腕症候群の場合の多くは、こりが拡がってきて、慢性化重症化してくると、首とか、鎖骨の下大胸筋のところ、それから肘の内外側、背中にまわると項(うなじ)のところ、肩甲骨の脇のところ、下半身では殿部、大腿部、ふくらはぎ、膝の内側、三里のつぼのところ、いろいろ多彩ではありますが、こういうところに叩打痛圧痛領域が出てきます(図5−1)。
多くの場合には左右対称的に拡がってゆく、人によっては片側だけに拡がる(図5−2)。
おそらくこの状態から左右、半身に拡がる傾向で、ほとんど全身に、正常なところがないくらいまで叩打痛領域が拡がってしまった患者さんもおられます(図5−3)。
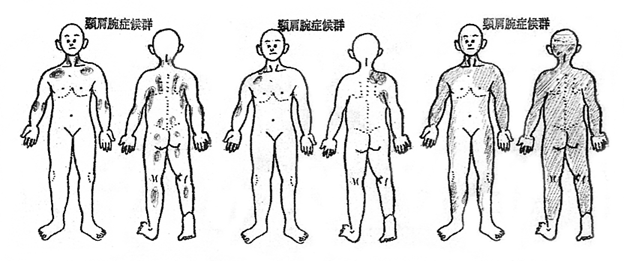
|
図 5-1
|
|
|
図 5-2
|
|
|
図 5-3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
図 5 頸肩腕 症候群にも叩打痛圧痛領域
|
|
|
|
診察で全身をくまなく触る、押してみるというのは非常にたいへんな作業なのですが、例えば顔や頭、首とか胸、脇、それに手の先とか足の先というのは触って探るというのはなかなか難しいのですが、叩くというのはわりと簡単なのです。
例えばおっぱいの周辺とかはきわどいですから、あまり触っていると患者さんも嫌がりますりが、叩打法のトントンだと、かなりきわどいことろでもくまなく検査できます。
叩打痛が全身的に拡がったケースの図ですが、見ると体毛のないところ全てに拡がっている。一時は体毛と関係があるのだろうかなどと考えたりもしましたが、そうでないのかも知れません。
叩打痛がほとんど全身に広がるという方も少なくなくて、そういう患者さんはもちろん例外なく重症難治化しています。叩打痛圧痛領域の筋・筋膜は全部硬くなってきますので、重症難治化がかなり続くと場合によっては関節拘縮が起きてきます。何人もの患者さんで肩関節が90度までしか上がらない。それも普通の四十肩、五十肩ではない。年齢も若いし、経過が違う。徐々に両側に起きるのです。
頚椎の運動制限、胸腰椎の運動制限は、軽重さまざまでほとんどの患者さんに起きています。
頚椎運動範囲では、これは患者さんによって制限される方向はいろいろです。オランダのある研究者は頭部回旋に注目していますが、東京厚生年金病院整形外科のドクターは左右屈の制限に注目しておられます。私の臨床観察ではさまざまです。再重症では全方向です。もちろん頚椎症は鑑別しての話ですが。
胸腰椎部の運動制限は、特徴があり、これは一番制限を受けやすいのは後屈です。
叩打痛の本態は何か
今までの話をまとめますと、疼痛過敏と言ったらいいのか、痛覚過敏と言ったらいいのか、ネーミングがまだ不確定なのですけれども、なんらかの痛覚が過敏になっているということが分かりました。
昔から整形外科の教科書にある叩打痛というのは、かなり強く骨に響くほどにドンドンと叩きまして、響いて痛いと骨の病気、昔は多かった脊椎の結核ですとか、今で言えば骨腫瘍とか骨の病気ではないかというのが教科書の記載なのです。
今日のテーマの叩打痛の場合には、指の頭で軽く叩く叩打法、叩打痛ですから、これを私は再発見したつもりなのです。
この方法は、全身くまなく触診で圧痛点を探っていくよりも非常に簡単迅速で、触診では触りずらいところも叩打痛では探ることができますし、圧痛検査ではおそらく検査者によってグイっと乱暴に押すドクターと、弱く押すドクターとの違いはありますけれども、そういう差はない、再現性が高い。したがって、先ほどからカルテの図でお見せしましたけれどもカルテで記載することも正確、簡単です。圧痛点の場合は(トリガーポイント)と言うのですけれど、それに比べると、叩打法、叩打痛のほうが有利だと思います。
しかし圧痛点は、確かにあるのです。叩打痛領域でないが、圧痛点だというのはやはりあります、ていねいに触っていくと。しかし圧痛点は必ずしも叩打痛ではない、ということも分かりました。叩打痛領域というのは点ではなくて、その領域にはすべて、どこを押しても圧痛がある。
圧痛という概念は否定する必要はありませんが、圧痛点、圧痛領域というのは、叩打痛領域にくらべると、かなりあいまいなで、再現性に乏しいのです。叩打痛というのは、臨床的観察をもっと詳しく経過を追って見てゆくと、どういうことが言えるのかというと、叩打痛にも強弱はたしかにあります。
少し叩くだけで逃げて検査者の腕を払い除けるぐらいの痛みの場合もありますが、多くの場合はそのようなことはなくて、かなり強く叩いてもなかなか分からないこともあるのです。響くとか、不快だとか表現されることもあり、強くなれば痛みになりそうだと思われるケースもあります。
強弱は確かにあるのですけれども、その程度評価は今のところ困難です。客観的に表示することはできないので、叩打痛領域の範囲だけをカルテ記載するわけです。
叩打痛の現われるポイントは馴れてくると大体分かる、というくらい好発ポイントがあります。そして叩打痛領域は、皮膚・脊髄・神経の、要するに脊髄神経や末梢神経の支配領域とは一致しません。それから広がり方には左右対称の法則と、半身側の法則などがあります。何年か前の頚椎捻挫で右側の項背部に叩打痛が現れると、何年か後の腰痛ではやはり右側に叩打痛が現われる。人間の体には右右という法則と、左右対称という法則が二つあるように思えます。そのような法則は決めなくてもいいのですが、僕にはそのような法則があるように見えます。これは、叩打痛の出現、拡大には脊髄以上の中枢神経系が関与しているらしいという説の、ひとつの根拠です。
それから痛覚過敏と言うことですけれども、皮膚の痛覚ではないのです。
叩打痛領域の表在知覚は、まず触覚、皮膚の表面を刷毛で触って調べますが、触覚と言います。それからピンで軽くつつくのを痛覚と言います。それから冷たいもの、冷たい金属で触っていますけれども、温度覚。これらの検査を叩打痛領域で調べてみますと、それぞれ、鈍のこともありますし、過敏なこともあります。両方あります。基礎疾患の時期によって、急性期と慢性期とかいろいろな時期によっても違うかもしれません。
叩打痛は筋筋膜痛を反映している
では、この叩打痛というのは何なのか、どの組織の痛覚過敏なのかということなのですが、皮膚・皮下組織の更にその下の層、すなわち筋・筋膜にほぼ一致するかなというのが、指先で軽く叩いて検査してみて、また皮膚知覚も検査してみた臨床観察からの一つの結論です。
筋・筋膜というのは、表面の皮膚から見ると、一番表面にある筋・筋膜から一番深いところの筋・筋膜まで多数の階層があるわけです。
叩打法というのは、その比較的浅い筋・筋膜を刺激しているのだろうという印象を持っています。
さて叩打痛領域は、筋・筋膜がまったくないわけじゃないけれども筋肉が乏しい指先や足の先まで波及することもあります。ですから、痛覚過敏になっている組織は筋・筋膜だけではなく、皮膚も巻き込まれているだろうと考えています。
それから叩打痛の再発の問題。再発の場合は、いったんは改善して消えた叩打痛領域が、再発ではいきなりいっぺんにどっと再出現する傾向があります。この現象は、個々の筋・筋膜が記憶していたということは考えづらいので、脊髄あるいは脳の中枢に記憶されている「防衛反応」ということが考えられます。全くの仮説ですが。
タッピングペイン マップ
叩打痛圧痛領域のネーミングのことですけれども、これでは地味だし分かりづらい。
この会もリサーチセンターというカタカナを使っていかないと、世界に発信するという構えにならないですね。
日本国内だけでもこういうことを、過労性疾患は、身体病であって立派な身体的他覚的所見があるのだということを認めてもらうのがなかなか難しいのですけれども、頸肩腕障害に関しては日本はダントツの先駆、先進国ですが、海外でも日本と同じようにあることは当然だと思います。
韓国とか台湾の報告はまだあまり見ていませんが、ヨーロッパ、アメリカでは産業医学の重要問題と見なされて久しいです。
叩打痛という言葉は日本の医学教科書には昔からあるわけですけれども、もちろん英語でもドイツ語でもそういう言葉はあると思います。しかし旧来の叩打痛は、骨の病変の検出法ですから、今私が提唱している叩打痛とは違います。それでネーミングも考えまして、他の国でのコンセンサスを将来は得たいということです。
タッピングペイン、タッピングペインマップ。診察して先ほどのような身体図の上に叩打痛の分布を描くことを、タッピングペインマップとして一つの診察法として確立したいと考えています。マッピング・オブ・フィンガータップペインでもいいのですが。
日本語にすれば叩打痛領域検査法ということになるのですけれども、これをもっと更に詳しく検討して、またネーミングも確立してゆきたいと思います。
以上で私の話は終わりますけれども、以上のことから、頸肩腕障害は身体病であってこうすれば立派に他覚的所見も把握できる。また頸肩腕障害は過労性疾患であって、慢性疲労の具体的現われのひとつのでもあり、また慢性痛のひとつの典型でもある、という渡辺仮説を最後に強調しておきたいと思います。
| 社会労働衛生 2003年第 1巻 2号 |
|
| 職業性疾患・疫学リサーチセンター |
|